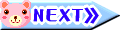● ずぶ濡れの雨宿り(2/3) ●
好きな人に八つ当たりなんかしちゃいけない、ヴィトスだって疲れてるだろうし、そう
思ってるのに自分の声はとげとげしくなっていく。
「第一、ヴィトスだって燃える物持ってないじゃない。服濡れてるのにどうすれば……」
いきなり、ヴィトスが服を脱ぎ始めた。それを見てあたしの声が途切れる。
ベルトを外して、青い上着を脱ぐ。それから、下に来ていた黒い長袖のシャツ……、って、
ちょっと、それ脱いだらヴィトス、はだか、はだか!
「んっ?」
あたしが口をぱくぱくさせているのを見て、ヴィトスはおかしそうに笑う。
「なんだい、ユーディット。これ以上見るんなら見物料を取るよ」
「け、見物って別にあんたのは、は、裸が見たい訳じゃ……」
見たい訳じゃないのよ、多分。見たい訳じゃないの、それなのに目が離せない。
初めて目にしたヴィトスの上半身はすべすべで、薄く筋肉が付いてて、おなかは真っ平らで、
このままヴィトスに抱きしめられでもしたら、あたしは頭が沸騰してしまうかもしれない。
「ユーディット、そんなに見つめられると、さすがに恥ずかしい」
困ったように照れ笑いを浮かべ、ヴィトスは自分のシャツをしぼった。
「あっ、あ……、あぁ、うん」
こわばってしまった身体と言うか視線を、ぎくしゃくとヴィトスから背ける。
落ち着かなきゃ、落ち着かなきゃ、って頭の中で繰り返してから、ヴィトスはあたしの事
好きでも何でもないかもしれないから、急に抱きしめられたらどうしようなんてそんな
心配しなくていい、って結論に思い至った。
そう思ったら妙に冷静になってしまって、やっとあたしも服を脱いでしぼらなきゃ、って
現実的な方に発想が向かった。
ヴィトスに完全に背を向けてから濡れた帽子を取ると、頭が軽くなる。
今日は肩を抱いてもらったりして嬉しかったけど、それは偶然のハプニングなんだから。
所詮、あたしの片想いなんだから。
それから上着を脱ぐ。その下に来ていたシャツも、スカートもストッキングも靴の中も
ぐじゃぐじゃだよ。着替えもないし、どうしよう。
「ねえ、ヴィトス……」
振り返ると、ヴィトスは顎に指を当て、こちらをじっと眺めていた。
「えっ?」
どきん、と胸が高鳴る。
「いや、君が僕の着替えを見つめていたから、僕もお返しに君を見ていたんだ」
「えええっ、な、何で」
着替えと言ってもあたしは帽子と上着しか脱いでない。それなのに、頬がかあっと熱くなってく。
「何でって、僕だけ見られるのは不公平だろう?」
そう言うヴィトスはブーツまで脱いでしまって、ズボンだけの格好になっている。
「ほら、ユーディットも脱いで、脱いで」
「脱いでって、ちょっと待って」
ヴィトスが近付いてくる。思わずあたしは後ずさると、すぐに背中が洞窟の壁に触れる。
目頭が熱くなって涙が滲みそうになる。そんな、ヴィトスの前で服を脱ぐなんて、やだよう。
「……」
やっとの思いであたしは首を左右に振る。そうしたら、ヴィトスは急に背中を向けてしまった。
それから自分の荷物を探り、そこからたたんだ薄手の毛布を持って戻ってくる。
「すまない、いつもの冗談のつもりだったんだが。頼むからそんなに怯えないでくれ」
そして、毛布をあたしに向かって差し出した。
「君の毛布は濡れてしまったようだが、僕のは比較的無事に済んだらしい。これを使うといい」
毛布を押し付けられ、あたしがそれを手に取る。そうしたらヴィトスはまた離れて行った。
「えっ、だって、ヴィトスは?」
「僕は大丈夫だよ。それよりも、濡れた服を着たままでいると風邪を引く。僕は君がいいと
言うまでそっちを向かないから、服を脱いで毛布にくるまってくれ」
冗談って、そんな冗談無いわよ。何だかあたしまでちょっぴり、変な考えしちゃったじゃない。
ヴィトスが、ええっと、あたしに……、とかねえ? でも、それでも良かったかな、とか?
頭の中で、ものすごくどうでもいい事、矛盾とまでは言えないくらいのくだらない考えが
ぐるぐる回っている。
あたしはそんな考えが勝手に沸き上がって消えて行くに任せながら、それでもやっぱりヴィトスに
背を向けて、アンダーシャツの裾に手をかけた。
「ううっ、冷たい」
濡れた服がぴったりと貼り付いていた所は、まあ体温とほとんど同じ温度になっているから、
どうって事はない。問題は雨に濡れつつ身体から離れていた布。冷たい水分をたっぷり吸って、
それが肌に触れると身震いしてしまう。
シャツを脱いで、すぐに肩から毛布を被る。これで、もしヴィトスがこっちを向いても身体は
見えない筈。それから、毛布が落ちないように背中を丸めながら、水が溜まっているブーツを
脱ぎ、ぴったり貼り付いているストッキングを脱ぐ。
「……」
そこでちらりと後ろを向いて、ヴィトスがこちらを見ていないのを確認する。あたしから
少し離れた壁際に座っているヴィトスは上半身裸で、濡れているズボンははいたまま。
肩を丸めて自分の手で自分の身体を抱きしめ、寒そうに肌をこすっている。
「あ」
いけない、つまらない事を考えてる間に、ヴィトスが凍えちゃうよ。あたしは慌てて
腰に貼り付いているスカートを脱いだ。恥ずかしいけど、そんな事気にしてられない!
「ヴィトス」
「うん?」
後ろから彼に近付き、声をかける。ヴィトスは律儀にも振り返らない。
「あのさ、毛布ごめん。半分こしようよ、ヴィトスもズボン濡れてるでしょ? 脱いで、さ」
ズボンを脱いでなんて、とんでもない事を言うあたしの声が震えてるのは寒さのせいだけじゃない。
「半分こって。毛布を切るのか?」
「違うよ、一緒に毛布に入ろうよ。ヴィトスだけ、寒い思いさせるのやだよ」
あたしはなるべく身体が毛布から出ないように気を付けながら、ヴィトスの隣りに座った。
「いや……、さすがにそれは。僕は大丈夫だから気にしなくていいよ」
「大丈夫じゃないよ、早くしないとヴィトスが風邪を引いちゃうよ。あたし、目をつぶってるから」
そう言って、二、三度まばたきをして見せる。
「いや、でも」
あたしは、ヴィトスの腕に手を伸ばした。
「きゃっ、冷たい!」
彼の腕のあまりの冷たさに、小さい悲鳴を上げてしまう。
「だめだめっ! 脱いで、今すぐ脱いで。一緒に暖まろう?」
「ああ、うん、でも」
「でも、じゃない! ほらほらっ」
片手でしっかりと毛布を握りしめ、座ったままぐずぐずしているヴィトスのズボンの腰に
もう片方の手をかける。
「分かった、分かったよ」
困ったようにヴィトスがそう言ったから、あたしはしっかりと目を閉じた。
「見てないからね。安心してね」
「まあ、君に見られてもどうって事はないが」
え? そうなの? じゃ、少しだけ見ちゃおうかな……、なんて、うそうそ。
それから、ごそごそと布のこすれる音。
「ええと、脱いだ、が。それじゃ、失礼するよ」
「うん」
ヴィトスの手が、毛布越しのあたしの肩に触れる。それだけでどきっとしてしまって、でも
またびっくりしちゃうとヴィトスが毛布に入らないとか言い出しかねないから、あたしは
がんばって身体が震えないようにこらえていた。
「僕も、見ないから」
「うん」
そう言って、すぐに毛布の端を持ち上げ、ヴィトスがあたしの右側に滑り込んでくる。
「きゃっ!」
肩に触れた彼の腕のあまりの冷たさに耐えきれず、あたしは短く悲鳴を上げてしまう。
「あっ、すまない。いきなりで」
「ヴィトス冷たいよ! 身体、冷え冷えじゃない」
こんな寒い思いしてるのに、ヴィトスはあたしに毛布を貸してくれたんだ。そう思うと、
何だかじんとして、目頭が熱くなってくる。
「まあ、僕も普段は冷血漢とか色々言われているからね」
「そういう意味じゃなくて、もう」
お互いしっかりと毛布を巻き付け、その中で並んで座った身体がぴったりと触れ合っている。
恥ずかしい気持ちももちろんあるけど、あたしが目を開けたらすぐそこにヴィトスの紫色に
なったくちびるが見えて、そっちの方が心配になって。
「あたし、ヴィトスよりあったかいから。あたしにくっついて」
くっついている身体を、更にヴィトスに寄せる。
「くちびる、真っ青だよ。どうしよう」
それから、あたしはゆっくりとヴィトスの頬に左の手のひらを当てた。
「このままいれば、まあ、暖まるだろう」
「うん、でも」
そのまま、ヴィトスの口の端に指を滑らせる。ヴィトスの肌をこれだけ冷たく感じるって事は
あたしの手の方がずっとあったかいって事だもん、そう思って少しでもヴィトスを暖められる
ようにって、優しい動きになるように心がけて、そっとマッサージをする。
「くすぐったいよ。何だか、変な感じだ」
ヴィトスのくちびるが動くと、そこに触れているあたしの指もくすぐられるような感じがして、
あたしも変な感じがする。
「もっと、くっついた方がいいのかな」
ヴィトスの頬やくちびるの端をさすりながら、あたしは右手をヴィトスの背中に伸ばした。
「ね、ほら……」
その手にぎゅっと力を入れる。彼の身体を抱き寄せるように、あたしの身体がくっつくように。
その時、ヴィトスが身体をすくませた。
「やっぱり、やめておこう」
「へ?」
思わず間抜けな声を出してしまうあたしにかまわず、ヴィトスはあたしの手から逃げようとする。
「ちょ、ちょっと待ってよ」
毛布から出て立ち上がろうとするヴィトスの腰に手を当て、あたしは慌てて引き留めた。
「寒いって。毛布から出たら凍えちゃうよ、ヴィトス」
「いや、その。だからと言って、まずい」
「まずいって、何が」
「何がも何も……」
照れたような彼の顔。ちょっぴり可愛いとさえ思ってしまった。
「その、やはり、こういう状態で同じ毛布にくるまる、って言うのは」
こういう状態、って……。そんな風に言われると、何だか急にものすごく恥ずかしくなって
きてしまって、あたしは何も言えなくなってしまう。そんなあたしを見てヴィトスも
すごく困ってしまったみたいだった。