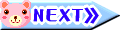● 少し遅れた誕生日(1/2) ●
「ふうーっ」
採取場から安全な街外れへと帰ってきたユーディーは立ち止まってから大きく伸びをした。
「今日は大収穫だったなあ。ヴィトス、どうもありがとう。お疲れ様」
欲しい材料を充分に集めてご機嫌なユーディーは、護衛をしてくれたヴィトスに頭を下げる。
「それなりの賃金は頂いているからね。わざわざお礼を言われると恐縮だよ」
ヴィトスは恐縮とはほど遠い、人を食った笑みを浮かべた。
「んー、まあそれはそうだけど。でも感謝の気持ちは本当だもん」
「君の気持ちは分かったけれど、感謝なんかされても一文の儲けにもならないからねえ。
それでもどうしても君が頭を下げたいと言うのなら止めはしないが」
「ううっ、何でヴィトスっていつも偉そうなのよー」
あははと笑うヴィトスに向かって拳を振り上げ、叩く真似をする。
「まあいいや。さて、材料が悪くなる前に工房に戻って調合しなくっちゃ」
「ああ、僕も酒場に用事があるからそこまで付き合うよ」
「じゃ、一緒に行きましょ」
小さな橋を渡る時、さらさらと流れる川の音が耳に心地よかった。穏やかな風が髪を
くすぐるのも気持ちよく、ユーディーは目を細める。
「今日も良い天気だなあ」
図書館の前を通り、広場へと向かう。
「こういう天気なら街の外へ行くのも良い気分転換になるね。雨が降っている時に
ぬかるんでいる道を歩かされるのは勘弁して欲しいが」
「うん、足元が悪いのは嫌だよね」
つまらない話しをしながら歩いていると、すぐに古代の石樽亭の前に着いてしまう。
扉を開けようと腕を伸ばしかけたヴィトスが、ふとユーディーの方を振り向いた。
「ユーディット、僕に何か言う事はないかな?」
「え?」
突然尋ねられ、きょとんとしてしまう。
「あ、今日はどうもありがとう」
「それはもう聞いたよ」
「え、あの、他に何か」
ヴィトスが何を求めているのか全く見当も付かず、ユーディーは戸惑ってしまう。
「いや、何もなければいいんだ。じゃあな」
そう言うと扉を開けてさっさと中へ入ってしまった。
「ねえ、待って」
ユーディーに背を向ける前、一瞬だが彼の顔に落胆の表情が浮かんだように見えた。
それが気になったユーディーはすぐに後を追ったが、ヴィトスはすでに酒場にいた客と
挨拶を交わしていた。
「んー」
ヴィトスの言葉が気にかかるが、さすがに他人との会話の中に割り込むような非常識な
真似はできない。彼の様子を探るのもいやらしいような気がして、ユーディーはそちらの
方に視線が行かないようにしながら工房への階段を上がった。
「ヴィトスったら変なの」
自分の部屋に入り、ドアを閉める。材料でいっぱいのカゴを机の上に置いたユーディーは
もう一度ヴィトスの言葉を思い返してみる。
「あたしがヴィトスに言う事があるって? お礼も言ったし、他に何があるのかしら」
いつもだったらそんな遠回しな聞き方はしないのに、とユーディーは不思議に思った。
◆◇◆◇◆
そんな事があってから数日が経っていた。ヴィトスとは会ったり会わなかったり、
話しをしたりしなかったり。あの時のヴィトスの態度がどうも引っかかっていたが、
だからと言って正面切って尋ねる事もできなかった。
「別にあれからもヴィトスも変わらないし」
何か重大な話しなら、向こうからそれなりのアプローチがあってもいい筈だった。
「どうでもいい事だったのかな」
それにしてはあの時のがっかりした表情が気にかかる。普段のヴィトスだったらあんなに
隙のあるような顔を見せたりしないし、そもそも思わせぶりな言動でユーディーの気を
引いたりもしないだろう。
「でも気になるんだよなあ」
もう少しで思い出せそうな事が喉の辺りに引っかかっているような違和感。
「採取の後……、街に入る時、橋の上?」
あの時の状況を思い出しながらそれに関連する何かが無いか考えてみる。
「ラステルと初めて会ったのがあの橋の上だけど、それはヴィトスに関係ないし。
初めての採取はヴィトスと一緒だったけど、その事でもないよね」
うーんとうなって首をひねる。
「まあ、考えても分からないんだったら思い出す価値も無いって事かもしれないけど」
そうやって自分を納得させようとするが、どうにも落ち着かない。
「とりあえず、ヴィトスの事は置いといてお仕事しなくちゃ」
このまま正体の分からないわだかまりを抱えていても仕方がない。酒場で受けた依頼が
数件あったし、アイテムの調合作業に没頭すればもやもやした気持ちも忘れられるだろう。
「えーっと、納期はいつだったかな」
ユーディーは壁にかけてあるカレンダーの前まで歩いていくと、数字の上に自分が付けた
赤い丸印を指さしながら確認する。
「来週の鍵の日、琥珀湯5本。モンスター退治は無期限だからいいとして……、あれっ、
この印は何だっけ?」
今から数日前の日付。一月二日、その数字の横に控え目に書かれている、青い小さな星印。
「この日に間に合わせなきゃいけなかったお仕事あったっけ。ううん、無い筈よ、そもそも
お仕事の締め切りは赤い丸を書いてるんだし」
星印を指先でつついてみる。
「何か特別な事でもあったんだっけ。あ、そう言えばこの日は採取に行った日? でも
あたしいちいち採取に行った時に印付けるなんてしてないわよ」
青。採取。ユーディーの頭の中を断片的なイメージがぐるぐる回っている。
「そう言えば年開けて忙しいからいつもこの日を忘れるんだよね。って、この日って
何の日だっけ」
採取に行った、青いイメージの人。ヴィトス。
「ヴィトスの……、誕生日」
思考より先に口が動き、その言葉を聞いた自分が驚く。
「ヴィトスの誕生日だーっ!」
いつも忘れるから印を書いたのだった。『ヴィトスの誕生日』なんてはっきり書くのは
恥ずかしいから、彼のイメージである青い色で、それでも誕生日は特別な日だから
ちょっと気取った星印で。
「あ、もしかして。いや、そうよ。ヴィトスはこれを言いたかったのかも」
そう言えばあの日、護衛を頼んだ時にヴィトスは少し嬉しそうな顔をした……、ような
気がする。わざわざ誕生日に声をかけてきたユーディーに何かを期待したのだろうか。
「あたしってもしかしてお馬鹿? だってせっかくのヴィトスのお誕生日だったのに
一日潰させちゃったじゃない」
一年に一度の大切な日なのに、草や石ころを拾う作業に付き合わせてしまった。
「ああー、どうしよう」
頭を抱えてよろよろとした足取りでカレンダーの前から離れる。
「どうしよう、どうしよう……、って考えてても仕方ないわ」
ぶるぶると首を振り、しっかりと頷く。
「今からじゃ遅いかもしれないけど、おめでとうだけでも言いに行こう」
気合いを入れる為にもう一度頷くと、ユーディーは工房を飛び出した。
「ヴィトスーっ」
ばたばたと階段を駆け下りながら、丁度酒場にいたヴィトスに声をかける。
「やあ、ユーディット。今日も元気なのはいいけれど、階段を壊さないでくれよ」
いつものようにほんの少し意地悪い挨拶。
「壊さないわよ。あのね」
ヴィトスの正面まで走って行くと、彼の顔を見上げる。
「……」
視線が合った途端、何だか急に恥ずかしくなり頬が熱くなってしまった。
「あの、ね」
「また採取に行くのかな。護衛だったら引き受けるよ、僕も君といるとなかなか楽しいしね」
「そうじゃなくて、あの」
お誕生日おめでとう、それだけの言葉が何故か口から出てこない。自分が緊張しているのだと
認識した途端、身体が余計にかちかちに固まってしまう。
「あのね。あの、こないだはごめん」
「ごめんって何が。僕は別に君に謝られるような覚えはないよ」
小さく肩をすくめる。
「いや、そうじゃなくて、でも」
もしかしたら他人がいるから上がっているのだろうか、ふとそんな風に考えてしまう。
「来て」
酒場のママさんや雑貨屋のおばあちゃんが自分の言動を気にするとも思えないが、それでも
人前では気恥ずかしい。ユーディーはヴィトスの腕を掴むと自分の工房へと引っ張っていった。
「どうしたんだい、ユーディット。お茶でも出してもらえるのかな?」
「いや、そうじゃなくて。あ、飲みたかったら淹れるけど」
部屋に連れ込まれたヴィトスは落ち着きを無くしているユーディーを見て楽しそうだった。
「それは嬉しいね。でもまず落ち着いた方がいいよ、何を焦っているか知らないけど」
「あ、うん、平気」
何をこんなに慌てているのか自分でも理解できずに、それでもとりあえず頷いてみせる。
「あのね、この間はごめんね。忘れてた訳じゃないのよ、でも」
「忘れてたって何が? ……ああ、そうか」
「ひっ」
急にヴィトスの目付きが険しくなり、ユーディーは短く小さい悲鳴を上げた。
「君もいい覚悟をしているね。忘れていただって? そんな簡単に済まされる事だと
思っているのかい」
「あ、あわわ」
低い声ですごまれ、思わず一歩後ずさってしまう。
「本当に悪気はなかったの。忘れるなんてとんでもない事してごめんなさい」
目に涙を浮かべるユーディーを見て、ヴィトスは表情を和らげた。
「いや、僕こそごめん。怯える君が面白くてついからかってしまった」
「ふぇ?」
先ほどの怖い顔はどこへ行ってしまったのか、ヴィトスはにこにこと笑みを浮かべている。
「忘れていたって借金の返済をかい? 取り立ての時期にはまだ早かったと思うけれどな」
「えっ、あ」
一瞬頭の中が空白になりかけたが、ヴィトスはユーディーが何の事を言っているかも
分からずに調子を合わせたのだと理解する。
「他に君が忘れて僕が困る事が何かあったっけ。正直全然思い当たらないんだが」