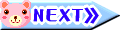● 3年後の約束(1/2) ●
ラステルは一番大切な本を手に取ると、気持ちの良い風の吹くバルコニーへ出た。
真っ白いテーブル、真っ白い椅子。ユーディーと何度もお茶を飲み、楽しいおしゃべりを
したお気に入りの場所。
「……ふう」
ユーディーが元の世界へ帰ってしまってから、そこはラステル一人だけの場所になった。
いつもユーディーが座っていた場所をちらりと見て、当たり前だがそこに親友の姿が
無いのを確認して寂しい気持ちになる。そしてお行儀良く自分の椅子に座り、内容は
さっぱり分からない錬金術の本を眺める。古くて紙がくすんだ黄色がかっているその本の
著者は、ユーディット=フォルトーネ。
「でも本当に不思議ね」
ユーディーが過去に帰った数日後、図書館でその本を見つけたのはポストさんだった。
蔵書に詳しいポストさんでも図書館の全ての本の存在を把握している訳ではない、それでも
その本はポストさんが普段見慣れている場所から見つかった。
『以前はその棚にそんな本は無かった筈なんじゃ』
少し自信が無さそうに笑っていたポストさん。
『まるでこちらに見つけて欲しいかのように、背表紙が光ってな』
背表紙に貼ってある金箔が光の加減で瞬いたらしい。気になったポストさんがその本を
手に取り、表紙の著者名を見て驚いたという訳だ。
『この本はお前さんが持っていた方がいい。きっと彼女もそれを望んでいる筈じゃ』
そう言ってポストさんはラステルに本を渡してくれた。
「ユーディーの書いた本」
書いてある内容はよく分からなかったが、中和剤や素材の植物、鉱石など、ユーディーの
口から聞いた事がある物や、一緒に採取した材料の名前が活字になっているのを見ると
とても嬉しかった。
「過去に帰って頑張ったのね、ユーディー」
竜の砂時計についてもイラスト入りで書かれている。そのページを見ると手が震えて
涙が溢れてしまうので、目印にしおりを挟んで避けるようにしている。
ユーディーにとっての未来、ラステルのいる世界に来た事はあまり詳しく書かれていない。
時間を移動するというのはそれだけ特殊な事例なのだろう、ただ『遠い場所へ行った時の
研究』と称して巨大ドラゴンや魔王をにおわせる記述がある。
「ユーディーって頭が良かったのね」
そんな失礼な感想が浮かぶ事もある。いつも元気に笑っていて、平気でとんでもない失敗を
していたユーディーの姿とこの真面目な研究書の接点が見つけられない。
「ユーディーに会いたいな」
決して叶えられない望みをつぶやくと悲しさがこみ上げて来て、喉の奥が押しつぶされる
ような気がした。
「……ユーディー」
テーブルに開いたままの本を置いて、ユーディーと過ごした輝くような時間に思いを馳せる。
「私、本当にユーディーといつまでも一緒にいたかったのよ」
ユーディーがいなくなってからの無味乾燥な生活。思い出にすがり、過去にしがみついて
前に進めない。起きている時は何をしていても、寝ている時は夢の中までもユーディーを
想い続けている。
「私は前になんか進みたくない」
二人が離ればなれになった後、独立した未来を歩むよりも、ラステルは自ら進んでユーディーの
呪縛に囚われ、澱んだ思考の檻の中で過ごしている方が幸せだった。
「でもユーディーは、私とさよならした後頑張ったんだよね」
ユーディーは彼女自身の道を進み、その証拠にこんな立派な本まで作った。
「ユーディーは私がいなくても平気だったのね」
少し意地悪くそんな事まで考えてしまう。
「……私の事、忘れてしまったのかしら」
もしかしたら自分の名前でも書いてくれているのではないか、本を受け取った時、そんな
事を思って胸をときめかせながらページを繰った。しかし、本文のどこにもラステルの
名前は記されておらず、全てのページを読み終わる頃にはラステルの胸はちぎれそうな
くらいの悲しみで満たされてしまったのだった。
ただ一ヶ所、気になる場所はあったが。
「これ、何なのかしら」
本の最後のページにかすかな染みがある。最初はただのインク汚れかと気にしないでいたが、
何度も繰り返し見ているうちに文字のように思えてきた。
「Jと、R」
汚れを指でなぞる。それはJudithとRastel、二人の頭文字。
「でも、そんな筈ないよね」
もしユーディーなら、こんな風にこすったら消えてしまいそうな儚い文字は書かないだろう。
「ユーディーは本当に私の事忘れちゃったのかしら」
自分はこんなにユーディーの事を考えているのに。いつもいつも想っているのに。
「そんなの嫌よ」
二百年の年の時を超えた友達、あの時ユーディーは確かにそう言った。
「そんな友達なんて、ステキでも何でもない」
今、ここにいて欲しい人がいないのに。これから一生会えないのに。それのどこが
ステキだと言うんだろう。
「ユーディー、私はユーディーの事をこんなに想っているのに」
ラステルの瞳にじわりと涙が滲む。
「どうして過去に帰ってしまったの? どうして私の側にいてくれなかったの?」
明確な答えが返ってくる訳もない問いを重ねる度に、ラステルの気持ちが押しつぶされていく。
「ユーディーにとって、私の存在は何だったのかしら」
それでもここにいないユーディーへの問いかけを止める事ができず、ラステルはかすれた
染みを指でなぞりながら、つぶやいていた。
「私にとってユーディーは人生の全て、いいえ、自分の人生より大事な人だったのに」
今ここに竜の砂時計があれば、全てを投げ打ってユーディーのいる場所へ飛んでいくのに。
「……」
そう考えてから思い直す。自分は本当にそれだけの覚悟があるのか。家族や家、住んでいる
メッテルブルグの街を捨てて、見知らぬ時代の見知らぬ村へ一人で行けるのか。
「本当に、ユーディーと行く覚悟があれば、あの時」
ユーディーがヴェルンの森の奥で砂時計を掲げた時、彼女の腕にかじり付いてでも止めれば
良かった。止められないなら一緒に行けば良かった。
「でも、私は何の行動もできなかった」
あれこれ頭の中で考えてはいるが、ユーディーに対する自分の想いは所詮そこまでのもの
だったのではないか。
「そんな私が、今更あれこれ言っても仕方がないよね」
仕方がないのは分かっているが、分かっているからこそ流れる思考を止められない。
「……ふう」
ラステルは本を閉じると、目をつぶって顔を空に向けた。
「気持ちいい風」
こんな風が吹けばユーディーのしなやかな髪が揺れて、いつも彼女の隣りにいるラステルの
頬を優しくくすぐったものだった。
「ユーディー」
何を見ても、何を感じても全てがユーディーの思い出へと結びついてしまう。
「ユーディー、何でいなくなってしまったの? ユーディーのいない世界なんて嫌よ。
ユーディーが私の隣りにいてくれない人生なんて何の意味もない」
ラステルの頬に涙がひとすじこぼれた。
「生きていたって楽しくも何ともないわ。ユーディー、会いたい、会いたいよ」
ゆっくりとうつむき、両手で顔を覆うと声を押し殺して泣き続ける。
「うっ、ひっく」
次々溢れてくる苦くて重い涙はラステルの目を焼き、喉にこみ上げる嗚咽はやわらかい
粘膜を傷付けるようだった。
「……」
それでも、やがて涙が止まる。泣きすぎて頭が痛くなってしまったラステルは、ユーディーの
身体に触れられない代わりに、彼女の書いた本にそっと手を当てた。
「あっ」
それからふと思い立ち、少しよろけながら立ち上がる。部屋へ戻ってインクと羽ペンを
持ってくると、また椅子に腰かけて本を開いた。
「この染み。消えてしまいそうだけど」
気にしないでいれば見えなくなってしまいそうな、あるのかどうかも分からないような
薄い汚れ。ユーディーの人生にとって自分の存在は、そんな取るに足りないちっぽけな
染みのような物だったのではないか、そんな風に考えてしまった事もある。
「こうすれば、ずっと消えないよね」
彼女の本に手を入れるのは罪悪感を伴う行為だったが、ラステルはインクビンのフタを
開けるとそこに羽ペンの先を差し込んだ。
「ユーディット=フォルトーネ。ラステル=ビハウゼン。こうやって書いておけば」
かすれた染みをなぞりながら、二人の名前を書き並べる。
「こうすれば、ずっとユーディーの本には、私達二人の名前が」
たかだか一冊の本に名前を書いたからどうなると言うのか。こんな事をしたからと言って
今は届かない場所にいるユーディーの心にラステルの存在が刻まれる訳でもないのに。
「私達、の、名前が……」
何の意味も無い行為。意味が無いどころか、余計にラステルの心は苦しくなってしまう。
ラステルの瞳に新しい涙が浮かび、視界がぼやけて行く途中、風が本のページを揺らした。
「えっ?」
風だと思ったが、今、自分の肌や髪には空気の動きを感じない。
「気のせいかしら」
しかし、確かに字を書いたページが不自然に揺れているような気がする。ごしごしと
目をこすり、ラステルはその動きを見つめていた。
「あ」
そのページはゆらゆらと持ち上がり、テーブルと垂直になった辺りで貼り合わせた紙が
はがれるように左右二枚に別れた。
「何? 何が起こっているの?」
一番最後だと思っていたページの後に、もう一枚現れたページ。
「これは何?」
しかもそこには文字が書き込まれている。ラステルはすぐにのぞき込んだ。
「これは……」
本文に使われている活字ではない。ラステルが良く知っているユーディーの丸っこい字が
少しだけ大人びたような筆跡だった。
『ラステルへ』
一番上に簡単な飾り枠付きで書かれた大きな字、それを見た瞬間、ラステルは目眩で
気を失いそうになった。
「嘘。嘘でしょ?」
破れてしまいそうな程に心臓がばくばくと高鳴っている。身体の芯から燃えてしまいそうな
程の熱が沸き上がってくる。
「嘘でしょう、ユーディー」
自分がユーディーを想うあまりに幻覚を見てしまったのではないか、本当に目の前に
あるのはただの白いページで、自分の心が勝手に文字が書いてあるように見せているのでは
ないだろうか。そんな事を考えながらもラステルは震える手を本に伸ばした。
『ラステルへ』
字に指を触れたらその瞬間蒸発して消えてしまうかも知れない、そんなおかしな妄想に
怯えながらラステルはユーディーの字を読み進めていく。