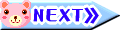● 大切な人(2/3) ●
「ああ、だから、君と僕が泊まる部屋はここだよ」
「えっ。お、お部屋は別々でしょ?」
頬を赤くしたユーディーがヴィトスの手から逃れ、数歩離れる。
「いや、部屋は一つしか取っていないけど。まずかったかな?」
「まずかったって、そんな。ヴィトスと一緒のお部屋で眠れる訳無いじゃない!」
ユーディーはヴィトスが別々の部屋を手配したものだと思っていたらしい。やっとそれに気付く。
「だって、二つ部屋を取るより一つの方が安いじゃないか」
「それはそうだけど、だってベッドだって一つしか無いわよっ」
きれいなシーツカバーのかかった、シングルサイズより幅の広いベッドを指さす。
「一つあれば充分だろう」
「充分って、一緒に寝るつもり、なの?」
首や耳の方まで真っ赤になったユーディーは自分の言った言葉が恥ずかしかったらしく、
困ったようにうつむいてしまった。
「キャンプしている時も一緒に寝ていたじゃないか。何か問題があるのかい?」
「問題って、い、一緒に寝た……のは最初の日だけじゃない。後は一緒って言っても
少し離れた場所で別々だったし。それに、お外でキャンプするのと、お部屋で、その、
ベッドで寝るのは違うわよ……」
徐々に歯切れが悪くなり、最後の方はもごもごとくぐもった言葉になる。
「同じだよ。僕は気にしない」
「あたしは気にするの。んもーっ、部屋替えてもらう!」
照れ隠しとも受け取れるような怒った表情を見せてから、くまさん入りのリュックを
ヴィトスに押し付け、ユーディーは一階への階段へと走って行った。
ユーディーの後を追いかけて行く訳にもいかず、大きなリュックを抱えたまま、ぼんやりと
彼女の帰りを待つ。
「ヴィトス〜!」
やがて、意気揚々とした笑顔で階段を上がってくる。
「やあユーディット、お帰り」
「部屋、替えてもらえるって! それでね、宿泊料の相談したら、一部屋分のお値段では
無理だけど、二部屋分よりは安くしてくれるって。やったね!」
「ああ、そうなんだ」
「最初にヴィトスが取ったお部屋よりは狭いけど、お互い一人で寝るんだからいいよね」
若干肩を落としてしまうヴィトスに気付いているのかいないのか、ユーディーは彼の手から
大きなリュックを取った。
「あたしの部屋はあっち。ヴィトスの部屋はそっち。じゃ、おやすみなさい」
簡単に指し示し、さっさと自分の部屋へと去ってしまう。
「……うーん」
一人取り残されたヴィトスは、小さくうなると自分に割り当てられた部屋へと歩いて行った。
翌朝、身支度を整えたヴィトスが部屋を出る。階段の上から一階を眺めたが、そこに
ユーディーの姿は無い。まだ眠っているのだろうかと思いつつ、彼女の部屋のドアを
ノックするが、返事は返ってこなかった。
「まだ起きていないのかな」
女性の部屋に勝手に入るのは失礼だと分かっていながらも、ベッドの上で無防備な格好を
晒しているであろう彼女の寝起きを見たい好奇心が勝ってしまったヴィトスはドアを開けた。
「ユーディット?」
「……」
くまさんを抱えてうつぶせになり、肩まで薄い布団をかぶっているユーディーが自分の
名前に反応し、むにゃむにゃと何かをつぶやいている。
「ユーディット、朝だぞ。起きろ」
言葉遣いはぶっきらぼうながら、ユーディーの枕元に回り込むとそっと彼女の髪に触れ、
指先で銀紫色の髪を梳くように優しく頭を撫でた。
「う……ん」
起きかけの姿を見るのは初めてではないが、薄暗い洞窟の中で見るのと朝の光が差し込む
白く清潔なベッドの上で見るのとでは印象が全く違う。
「えっ、もう朝なのぉ?」
透けるような白い肌の上に髪がほつれかかり、そのせいでいつもより少し大人びて見える
ユーディーの、色っぽくも聞こえる声にヴィトスの手が一瞬止まる。
「全く寝ぼすけだな、君は」
低く小さな声でそう言いつつも、彼女の淡い眠りを邪魔しないような手の動きを再開させる。
「んっ……、あ、ヴィトス」
それでもしばらくすると、顔をゆるやかにヴィトスの方に向ける。ゆっくりと目を瞬いて
自分の髪を撫でている人物を認めた。
「ああ、お早う、ユーディット」
「お早う、でもまだ眠いの」
心地よいやわらかなベッドの上で少し恥ずかしそうに微笑むユーディーを見て、ヴィトスの
胸の奥に鈍く甘い痛みが走った。
「まだ眠いって、君、ずいぶん早く寝たじゃないか」
「うーん、だってあまり眠れなかったんだもん」
ぐしぐしと目元をこする。手の甲までを隠している袖は白くシンプルな寝間着のもののようで、
キャンプしている時はそんな寝間着は着ていなかったな、とヴィトスはぼんやり考える。
「ね、ヴィトスももう少し寝ようよ。お布団、気持ちいいよ」
とろけるような笑みを見せられ、
「ああ、そうだな」
素直に頷いたヴィトスはベッドの縁に腰かけると、手早く靴を脱いだ。うつらうつらと
また眠りの世界に引き込まれかけているユーディーの布団をめくり、彼女の手から
くまさんを取り上げてベッドの枕元に置く。
「やっ、くまさん」
くまさんを求めて腕を伸ばすユーディーの横にさっと自分の身体を滑り込ませ、彼女を
抱きしめようとした途端、
「えっ、何? きゃっ」
どん、と両手で突き飛ばされた。
「ふえっ」
ヴィトスを突き飛ばしつつ彼から逃れようとした後ずさったユーディーが、どすん、と
音を立てて反対側の床に落ちる。
「大丈夫か、ユーディット」
「……」
床に転がってしまったユーディーは、泣きそうな目でヴィトスを睨む。
「何するのよ、痛いじゃないっ!」
起き上がろうと思って布団の端を掴むが、なめらかな布はベッドの上を滑り落ち、
それにすがっていたユーディーは簡単にバランスを崩してしまう。
「痛いって、君が勝手に落ちたんだろう。それに、君が寝ようって言ったから」
「一緒に寝ようなんて言ってないっ! ヴィトスのばかーっ」
ベッドの上からユーディーを眺める。寝間着は長くゆったりしたTシャツだったようで、
裾の方がめくれあがって張りのある太ももが途中まで見えてしまっている。普段彼女が
身に着けているミニスカートの方がよっぽど短いが、これはこれで扇情的な格好だった。
「そうか。僕はてっきり」
だぶだぶして大きく開いている襟から、彼女の白い肌が見える。
「てっきり、何よ」
上目遣いでこっちを睨むユーディーは、恥ずかしいのと怒っているので頬を紅潮させている。
「いや……」
そんな彼女に見とれてしまい、ヴィトスは言葉を無くした。このまま、手を伸ばして
彼女をベッドの上に引き寄せ、細い身体を抱きしめて髪を撫で、それから……。
「もうっ、おかげでばっちり目が覚めちゃったわ。着替えるから出てってよ!」
ユーディーは立ち上がり、一晩自分が使っていたやわらかい枕の端を掴むと、それを
ばすん、とヴィトスに打ち下ろす。
「こ、こら、何をするんだ」
楽しい妄想を邪魔され、ヴィトスは我に返った。
「出てってって言ってるの! 聞こえなかった?」
更に数発追加され、仕方なくヴィトスはベッドから下りる。
「早く、早くっ」
「分かったよ」
いい加減に靴を履き、靴ひももろくに結ばないままでヴィトスは部屋から追い出された。
部屋を出て、靴をはき直してから手を背中に回し、ドアの横の壁にもたれて目を閉じて
ぼんやりと考え事をする。
「今日、メッテルブルグを出て数日でヴェルンに着くから、そうしたら酒場に寄って
情報の収集と割のいい依頼を……」
ヴェルンに帰ってからのおおまかな仕事の流れを考えていたが、頭の中で建物を考えると
そのドアや脇から、帰り道を考えると木の陰や自分の隣りに、赤い服を着た可愛らしい
少女の姿がちらちらと覗いてしまう。
「うーん」
想像の中のユーディーは、たまに先ほどの白い寝間着姿の時もある。大きなくまさんを
抱えていたり、笑っていたり、怒っていたり。
「……参ったな」
正直に言えば、頭からユーディーの姿や声が離れず、それでいっぱいになってしまっている。
ヴィトスがベッドの上で手を出した時、恥ずかしそうにその手を掴み、立ち上がって
自分の方へ倒れ込んでくるユーディー。抱きしめた時の甘い香り、揺れる髪の肌触り。
そのまま、ゆっくりと。彼女も最初は嫌がるかもしれないが、徐々に……。
「お待たせー!!」
突然の大きな声、バタンと開いたドアの音にヴィトスの空想が破られる。
「ああ、ユーディット」
閉じたまぶたの奥に浮かんでいたしどけないユーディーと、今目の前にいる元気なユーディーの
ギャップに一瞬戸惑い、返事が遅れる。
「やあねえ、どうしたの? 半分寝てたみたいな顔してたわよ」
きちんと服を着て、髪の毛もさらさら、帽子も真っ直ぐかぶってお出かけ準備万端の
ユーディーがにっこりと微笑んだ。
「いや、気にしないでくれ。さてと、出発するか」
「出発、出発〜。はい、くまさんよろしくね」
むぎゅっ、とリュックを押し付けられる。
「はいはい」
「返事は一回で元気よく、よ」
「はいはいはい」
「何で増えるのよ〜」
ぺしぺしと肩を叩かれる。彼女との無邪気なじゃれ合いが楽しくて、ヴィトスはユーディーを
からかい続ける。
黒猫亭を出て、中央広場から城門へ。
「あっ、サカナサカナ。コイ、フナ〜、あっ、ま、待ってよっ」
泳いでいるサカナを指さしていちいち名前を呼ぶユーディーを無視する振りをして先に
進むと、慌てて走り寄ってくる。
「せっかくあたしがおサカナの名前教えてあげてるのに、聞きなさいよ」
「聞く必要ないよ。それに、ほとんど知ってる」
「えっ、全部知ってるの? だって、ヌシいたよ、ヌシ」
「ほとんど、だよ。全部とは言ってない」
一瞬興味を引かれたが、街の堀にヌシと呼ばれるような生き物がいるとは思えない。
ユーディーが面白おかしく話しを作ってるのだろう。
来た時とは逆に街道を辿って行くと、まだたいした道のりもはかどっていないのに、
ぐったりとした様子でユーディーが立ち止まる。
「どうした」
「疲れた〜」
肩を落とし、背中を丸めている。
「まだ昼前だよ。それに昨日は宿屋のベッドで寝て、元気いっぱいに回復しただろう?
甘えた事を言うとここら辺に捨てていくぞ」
「いや、捨てられるのは、いや〜」
ぶんぶんと左右に首を振る。
「疲れたって言うか、眠い。あっ、ねえ、少しお昼寝していかない?」
「昼寝? 眠いってさっき起きたばかりだろう、何を言っているんだ、君は」
「ほらほら、あそこの木の下。日影になってるし、気持ちよさそう」
道の脇の方を指さし、さっさと走って行ってしまう。
「全く、君といると寄り道が多くてかなわない」
つぶやきつつも、ユーディーの後ろを追いかけた。
「ヴィトス、毛布出してよ」
「嫌だよ、面倒くさい」
「え〜っ、ケチ」
「第一、僕は眠くない」
確かに寝転がったら気持ちの良さそうな草の上に、ユーディーはぺったりと座り込む。
「じゃ、膝枕してよ。あたしがお昼寝する間」
自分の傍らに荷物を置いて反対側の地面をぺちぺちと叩いてそこに座るように促す。
「何で」
「何でっていいじゃない。それともあたしには毛布も無し、枕も無しで眠れって言うの?
ヴィトスってひどーい!」
「ひどいって、それこそひどい言いがかりだよ。そもそもよくそんなに眠れるな、君は」
「だからあんまり寝てないって言ったじゃない……、ふあぁ」
口元を手で隠し、大きなあくびをした。
「なるほどね、君はすっかり土の上、草の上が気に入ったと言う訳だ。宿屋の清潔で
やわらかなベッドがお気に召さない身体になってしまったんだな」
「何それ。違うわよ」
口を尖らせながら、それでもヴィトスが自分の横に座ると、嬉しそうに微笑んだ。
「違う? くまのぬいぐるみも持って行った筈だし……、あっ、そうか。あの宿屋で
有名な幽霊でも出たのかな?」
自分の荷物を脇に避け、ヴィトスはユーディーの苦手な幽霊話をしようとする。
「出てないわよっ」
軽く曲げていたヴィトスの膝頭に手の平を当て、ぐいぐいと押して地面に平らに伸ばさせる。