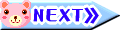● 深く結びつく想い(2/3) ●
!百合注意! 女の子同士のキスシーンがあります。苦手、嫌いな人は読まないで下さい。
ポストさんから、オヴァールへ。何だかいろいろ難しい話しになったけど、要するに
竜の砂時計はヴェルンの採取場の奥にある、石柱に囲まれた魔法陣の上で作用するらしい。
「あの石柱にそんなすごい力があったなんてねえ。まあ、氷室で見た時も何だか怪しいなあ
とは思ってたんだけど」
らしいと言うか、するかもしれない、って仮説だけど。
「さて、と」
図書館からの帰り道、中央広場の石畳の上に立ち止まり、あたりをぐるっと見回した。
静かな空気、かすかに吹いている気持ちの良い風。この街とも、ずっと住んでたあたしの
工房ともお別れか。
「荷物まとめなきゃかな」
まとめるって言っても、たいした物はないけれど。でも、後に迷惑をかけないように、
荷物の整理とお掃除だけはしておかなくちゃいけないよね。
「それと、お世話になった人への挨拶か」
護衛をしてもらったり、王国祭で遊んだり、便利な施設を使わせてもらったり。砂時計を
作るレシピのヒントをもらったり、本当にいろんな人にお世話になったんだよな、あたし。
でも、ポストさんにお別れの挨拶をして来いって言われた時、真っ先に浮かんだのは
ラステルだった。でも、思い浮かべたラステルの笑顔はすぐに崩れて、あの時の悲しそうな
泣き顔になってしまって。
「もう、会えないよね」
この間、メッテルブルグに行った時にラステルを見かけたの。大好きだっていう気持ちが
あふれて声をかけたかったけれど、それと同時にとても怖くなって、どうしていいのか
分からなくて、あたしはその場から逃げ出してしまった。
「……会いたいな」
もう一度、ラステルの顔を見たい。声を聞きたいよ。
自分が彼女を傷付けて、自分が彼女から逃げたのに、あたしって何て勝手なんだろう。
あたしの足は工房へは向かわずに、ラステルと初めて出会った場所、街外れの橋の
たもとへ進んでいった。
さらさらとそよぐ風、風に揺れる可愛らしい薄ピンク色の花、いねむりしている黒ネコ。
あの時とほとんど同じ風景なのに、そこにはラステルの姿だけが無い。
「ここに、危なっかしく立ってたんだよね」
橋の手すりにひじを乗せ、背を丸めて手の平であごを支えて川を眺める。
「てっきり飛び込み自殺しちゃうんだと思ったよ。本当にラステルって変わってる」
初めて会った時、可愛いけどすごく変な子だと思った。でも、あたしの話しを信じて
くれて、嬉しかった。
「あたしと友達になりたいって言ってくれて、自分の住んでる場所を教えてくれて、
メッテルブルグを案内してくれて」
楽しかったな。ラステルと一緒にいる時は、いつでも。
「はあ〜あ」
あたしは大きくため息を吐いた。いつからこんな風になっちゃったんだろう。いつから
ラステルをただの友達だって思えなくなってしまったんだろうって、そんな考えばかりが
ぐるぐると頭の中を回り続ける。
あの時、最初に砂時計の効力が発動されていたら。あのまま過去に逃げ出してしまって
いれば、こんな思いはしなくても済んだかもしれないのに。……ラステルを傷付けなくて
済んだかもしれないのに。
「さて、どうしようかな」
いくら考えてももう取り返しが付かない事を断ち切るように、これからの計画を練る。
工房に帰って、簡単に荷物を整理して。アルテノルトからプロスターク、リサへと
ぐるっと回って、お世話になったみんなに挨拶しよう。そんで、ヴェルンに戻って
来たら、きちんと荷物を片付けて、帰ろう。
「メッテルブルグは、どうしよう」
ラステルがいる場所には、行けないよね。ラステルはあたしに会いたくないだろうし。
それにまた、彼女の顔を見るとあたしは卑怯者のように逃げ出してしまうから。
ヴェルンのこの橋の上と、メッテルブルグにはラステルとの思い出がたくさん残ってる。
メッテルブルグの城門で、あたしをずっと待っててくれたラステル。あたしを見て、
嬉しそうに駆け寄って来てくれたラステル。
「……」
涙が出そうになって、あたしは手の平で自分の顔を覆った。
……あたしは、何の為にここに来たんだろう。自分が辛い思いをして、ラステルに悲しい
思いをさせて。
ラステルにキスしたけど、それはエッチな意味とかそういうんじゃ全然なくて、ただ
もっとラステルを近い距離で感じたかったから、だと思うんだけど。
誰かを好きになるってこんなに辛くて悲しい事なんだって、全然知らなかった。誰かを
好きになれば、その好きな人と一緒にいられれば幸せになれるって思ってたのにな。
一番最初にラステルと会った時に、戻れればいいのに。でも、ラステルとずっとすごして
来た時間は失いたくない。
頭の中にいろいろなつまらない考えがごちゃごちゃと浮かんでは消えていく。
「さて、帰ろうかな」
いつまでもここにいても仕方ないし。あたしはとぼとぼと、中央広場へ向かった。
古代の石樽亭のドアを開け、中に入る。
「きゃっ」
「おっと」
途端に誰かにぶつかった。
「どこを見て歩いているんだい、君は。危なっかしいな」
……ヴィトスだ。ヴィトスきらい。いつも意地悪するんだもん。
「ドアの前に突っ立ってるあんたが悪いんじゃない」
だからついつい、きつい言葉で言い返してしまう。
「そんな言い方はないだろう、ぶつかって来たのは君の方なんだから。ケガでもしたら
治療費を請求するよ」
なんか楽しそうに笑ってるし。あたしがこんな気分の時に、よく人をからかって遊べるわね。
すっごいムカつくんだけど。
「そんなの、ツバでも付けとけば治るわよーだっ」
あかんべえをしようと思ったけど、何だか涙がこみ上げて来てしまったから、うつむいて
早足でヴィトスの脇をすり抜ける。
雑貨屋さんのおばあちゃんにも、カウンターのママさんにも挨拶をしないで。ごめんなさい。
そのまま階段を上がり、工房へ……。
「あ」
工房のドアに、ラステルが寄り掛かって立っていた。
「ユーディー」
ラステルが口に出した名前の半分も聞かずに、あたしはくるりと振り返り、そのまま階段を
駆け下りる。外に逃げようと思ったのに、ドアの前にはヴィトスが立ちふさがっていた。
「どいてよっ!」
「……」
ヴィトスはそっぽを向いて知らんぷりをしている。なっ、どうしてこの人っていつも
こういう、人が困る事を平気で……。
「どいてってば、急ぐのっ」
ヴィトスの腕をつかんで引っ張ったり、横にぐいぐい押しても動いてくれない。
「ユーディー」
そしてすぐに、ラステルがあたしの側までやってくる。
「あっ、もう、……ばかあっ」
両の手に拳を作り、ヴィトスの胸をどん、と叩く。
「おっと、また治療費追加だな」
「知らないわよ、そんなの」
目にじわりと涙が滲んでくる。さっきまで、ううん、今でもラステルに会いたいって、
一緒にいたいって思ってる。それでも、彼女の顔を見られない。
「ヴィトスさん、ありがとうございました」
「いや。この程度、礼には及ばないよ」
「え?」
何でラステルがヴィトスにお礼を言うの?
「ユーディー、こっち来て。お部屋に行こう?」
ラステルの手があたしの手に触れる。ほんのりと感じるラステルの体温と、あたしの
肌を撫でる指の動き。
「でも」
「私、ユーディーにお話しがあるの。ね、お願い」
「ん」
ラステルのお願いには、どんな時でも逆らえないや。ラステルはあたしの手を握り、
そっと引っ張って彼女の方へと振り向かせた。
「大丈夫。……ね?」
ラステルは少し背をかがめ、あたしの顔をのぞき込んで優しく微笑んだ。
「……」
その声と笑顔が、あたしの心にじんわりと染みてくる。
「ラステル、ラステル、ごめんね、あたし」
途端に涙があふれて、止まらなくなる。
「あたし……、ラステルに、ラステル、ごめんね」
「ええ」
泣きじゃくるあたしの肩に手が回る。
「ほら、ユーディー、こんな所で泣くと、ヴィトスさんに笑われちゃうわよ」
「あっ、う、うん」
ちらっとヴィトスを見たら、本当ににやにや笑ってるし。信じられない。
「だから、お部屋に行きましょう。ね?」
うん、と頷いたあたしは、ラステルに手を引かれ、部屋への階段をゆっくりと上がった。
ラステルがあたしの部屋のドアを開ける。二人で部屋に入って、ラステルがドアを閉める。
「座りましょうか」
あたしの手をそっと握ったままラステルはベッドへ向かい、そこに並んで腰を下ろす。
「ユーディー」
涙の止まらないあたしの手を、両手でぎゅっと握り直してくれるラステル。
「ごめ……、ラステ……」
「ううん。私の方こそごめんなさい、ユーディー」
ラステルが何で謝るのか分からなくて、あたしは涙で霞む目を上げた。
「どうしてラステルが謝るの? だって、ラステルはあたしの事、……嫌いでしょ?」
「……」
ラステルは、今度はあたしの身体を優しく、それでもしっかりと抱きしめてくれた。
「ラステル?」
「ユーディーを嫌いになる訳ないじゃない。そんなの、絶対にない」
あたしの頬に、ラステルの頬が擦り付けられる。
「だって、この間、ラステルあたしの事嫌いだって」
「ごめんなさい、あの時は驚いてしまって」
それから、限りなくくちびるに近いあたしの頬に、ラステルは優しくキスをしてくれた。
ふわりとした、やわらかいくちびる。彼女に触れられた場所が、ちりちりと熱くなって。
「ごめんね。ずっとユーディーの気持ちに気付かなくて、あの時ユーディーの気持ちを
受け止められなくて、本当にごめんね」
何度も何度も、ラステルはあたしに謝った。酷い事をしたのはあたしの方なのに。
「私、ずっと考えたの。ユーディーの想い……、私の想い。私はユーディーが好きで、
ユーディーも私を好きでいてくれてるんだよね」
ラステルの目にも涙が滲んでくる。
「ユーディーは私の一番だし、私はユーディーの一番だよね?」
「……うん」
あたしは、ラステルの目を見てしっかりと頷いた。
「良かった」
そうしたらラステルは、本当に安心したように微笑んだ。