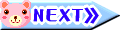● 放っておいてもらう方法(1/2) ●
さわやかな風がユーディーの工房の窓のカーテンを揺らす。
「んもうっ、ヴィトスったら酷いの。いーっつもあたしにばっかり意地悪するのよ」
ぷりぷりと怒りながら、ユーディーはラステルの手作りクッキーに手を伸ばした。
「んっ……、美味しいなあ」
一口サイズのクッキーをほおばり、サクッとした歯ざわり、口の中で溶ける上質の小麦粉と
バターの香りを楽しむ。幸せそうに微笑み、それからティーカップのお茶をゆったりとすすった。
「それで、ユーディーはどんな意地悪をされるの?」
テーブルの向かい側に座っているラステルはユーディーが置いたカップに新しいお茶を注いだ。
「あ、ありがとう。あのね、この間採取に行った事なんだけどね」
途中途中、話しが続けやすいタイミングでラステルは相づちを打つ。
「あたしは、がーっと植物とか鉱石を拾って、そんで後でまとめて選り分けたい訳」
両手で目の前の空間を大きく囲んでから、右の物を左に移す仕草をする。
「その方がいちいち立ち止まるより効率がいいでしょ? なのにヴィトスったらねえ、
クサイ花をカゴに入れるなとか、崩れやすい石なんか拾わなければいいだろうとか
いっちいち細かくケチ付けるのよ。もーっ、うるさいのっ」
「ユーディーにはユーディーのやり方があるものねえ」
「そうっ、そうなのよ。ヴィトスったらそこが分かってないんだなあ。でもラステルは
ちゃんと分かってるんだよね、だからあたしラステルって大好き」
大好きと言われ、ラステルの頬がほんのり赤くなる。
「うふふ、私もユーディーの事大好きよ」
「えへ、嬉しいなあ」
それから二人で見つめ合い、てれてれと微笑み合う。
「うーん、それにしても、どうにかヴィトスに放っておいてもらう方法は無いかな」
口元に親指を当て、ユーディーは考え込む。
「だったらヴィトスさんを護衛に誘わなければいいんじゃないかしら?」
もっともな意見を口に出すと、ユーディーは難しい顔になった。
「うーん、それは……、ヴィトス意地悪だけど、採取場では頼りになるし」
「そうなの。それじゃ、他の方法を考えないと」
ユーディーのヴィトスに対する愚痴は、聞いている分には仲の良いカップルののろけ、
態度のはっきりしない想い人に対する不満としか思えない。
最初のうちこそユーディーに想われているヴィトスに焼きもちに似た感情を持ったもの
だったが、最近では親友の心がヴィトスに傾いていく過程を見るのが楽しくて、
ラステルは彼女の話しを聞く為にお茶菓子などを携えてユーディーの部屋に通うのだった。
「うーん、何かいい方法は無いかなあ」
ユーディー自身はその感情を恋などとは思っていないだろうし、正直に言えば今でも
ちょっぴりヴィトスに嫉妬する心はあるけれど、やはり大好きな人の笑顔を見るのは
嬉しいものだし、本当の恋人同士になれば元の世界に帰るなどと考えなくなるだろう。
そんな打算も入っているラステルはユーディーにそれと気付かれないように、二人を
くっつける方向に巧みに話しを持って行く。
「じゃあ、そうねえ。護衛には雇うとしても、ユーディーがヴィトスさんを無視しちゃう
のはどうかしら」
何度か一緒に弱い敵しか出ない採取場へ行ったり、街から街へと移動した時に見た限りでは、
ユーディーがそんな態度を取った途端、ヴィトスは余計に激しくちょっかいを出して来るに
違いない、そう確信しての提案だった。ラステルがいる前での二人の会話、ユーディーから
聞く二人きりの時のやり取り。どこをどう見ても、ヴィトスもユーディーを過剰すぎる
程に意識している。
「ユーディーが反応するからからかわれるのよ。無視してたら向こうも気にしないわよ」
「うーん、そうねえ。それは逆にあたしの方が意地悪っぽくていいな」
「ね、そうでしょう?」
「うんうん、まあ最低限の会話をしない訳にはいかないけど、できるだけ口を聞かない
ようにすれば、ヴィトスもあたしに構わなくなるかもね」
多分、そんなユーディーを見たらヴィトスが放っておく筈がない。構いに構いまくるだろう。
その時にヴィトスの方からでもユーディーの方からでも、早く告白でも何でもして恋人同士に
なってしまえばいいのに、とも思う。
「ねえ、ユーディー」
「ん?」
新しいクッキーに伸ばした手が止まる。
「ユーディーは、いつまでも私のお友達でいてくれるよね。私と遊んでくれるよね?」
「えっ、何言ってるの? そんなの当たり前じゃない、当然だよ!」
ユーディーに彼氏ができれば、友達、つまり自分とは会う時間が少なくなってしまうだろう。
そんな含みに気付く訳もなく、ユーディーは大声で否定する。
「そう、良かった」
それでもやはり、彼氏の方を優先するんだろうな、そんな寂しさをこらえてラステルは
微笑みを浮かべる。
「うん。だってあたし、ラステルが一番大好きだもん」
「私もユーディーが好きよ。大好き」
お互いに伸ばした両手をしっかりと握り合った。
◆◇◆◇◆
ラステルと楽しいおしゃべりをしてから、ほんの数日後。
「それじゃ、出発しましょ」
ヴェルンの採取場に入る前、人気の少ない街外れの橋のそばで持ち物の確認をして、
ユーディーは護衛のヴィトスに声をかけた。
「うん、君がいいならいいよ。ところで、またクラフトが湿気っていたり、シチューが
腐っていたりはしないだろうね?」
明らかにユーディーをからかっている口調。
「ん、平気」
しかし、ユーディーは言葉少なに答えただけだった。
「……?」
そんなユーディーの様子にヴィトスは首をひねる。
「どうした、お腹でも痛いのか? どうせ拾い食いでもしたんだろう」
「だっ、誰が拾い食い……」
反射的に言い返しそうになるが、今日は一日ヴィトスを無視する計画なのでぐっとこらえる。
「別に。行きましょ」
「あ、ああ」
肩すかしを喰らったようなヴィトス。そんな彼の様子を見て、ユーディーは少し
良い気分になる。
採取場に入ると、いつもみたいに落ちている材料をやたらに拾い集めるのではなく、
以前ヴィトスに言われた通りに不要な物はその場で捨てていく。
「ユーディット、あの木の茂みにぷにぷにがいる」
敵を見つけたヴィトスが指さすと、
「……」
無言で水色ぷにに走り寄り、木の杖でぽくん、と叩く。
「緑ぷに、お願い」
「ああ」
短く指示すると、ヴィトスはナイフで簡単に緑ぷにを倒した。
「お疲れ」
敵を全てやっつけると、それだけ言ってヴィトスに背を向ける。
「……おい、ユーディット」
「きゃ」
突然肩に手を置かれ、うっかり短い悲鳴を上げてしまった。
「ユーディット、今日はもう切り上げて、街へ戻ろう」
「へ?」
振り向かされ、ヴィトスの表情の真面目さに少し驚く。
「何だか君、いつもの元気さが無い」
「別に、平気よ。あっ」
ヴィトスは手袋を脱ぐと、大きな手をユーディーの顔に寄せた。前髪を軽くすくい、
少し冷たい手の平をおでこに当てる。
「うーん」
「ひゃ」
おでこを覆っていた手の平が、今度はユーディーの耳元から首筋に移る。肌の上を
滑る指の動きに、ユーディーは首をすくめる。
「くすぐったいよ」
「熱が無いかみているんだよ。動かないで」
普段あまり聞いた事のない、落ち着いた優しい声。
「ん……」
その声に安心させられ、ユーディーは素直に肩の力を抜いた。
「大丈夫そうだな。ユーディット、立っていて辛くないか? 少し休むか」
「え、だから平気だって」
「平気そうには見えないよ」
ヴィトスはマントの飾りを手早く外す。マントを脱ぎ簡単にたたむと、それをそばに
生えている木の下、やわらかい草の上に敷いた。
「ほら、ここに座って」
「ヴィトスのマントに座る訳にはいかないよ」
「気にしなくていいから」
ユーディーの手を取ってマントの上に座らせ、自分もすぐ隣りに座る。
「寒気とかしないか、ユーディット?」
ヴィトスはユーディーの肩に腕を回し、自分の方へと軽く引き寄せた。
「あ、う」
自分の肩が、ヴィトスの身体に密着する。ヴィトスのさらさらした髪が揺れ、ほんのりと
熱くなってしまうユーディーの頬に触れる。
「……な、何?」
「何って」
赤くなっているかもしれない頬を見られまいと顔を片手で覆ったユーディーが挑むような
目付きを意識してヴィトスを睨む。
「何か、ヴィトス、変。何を企んでるのよ」
変と言うより、今までされた事の無いような優しい気遣いを見せられて、こちらがどういう
態度を取って良いのか分からない。
「何も企んでいないよ。それに、変と言うのなら君の方が変だよ」
「変じゃないわよ、あたしは……」
言葉を遮り、ユーディーの肩に回しているのとは反対の手で、またおでこに触れる。
「僕がからかっても乗ってこないなんて、頭でも痛いんじゃないのか? そうでなくても
どこか具合が悪いのかもしれない」
「別にどこも悪くないよ」
口を尖らせたが、おでこから離れる時に前髪をくすぐったヴィトスの指の動きが嬉しい。
このまま、ヴィトスと身を寄せ合い、彼に触れられていたい。
「ヴィトスの気のせいじゃない? あたしはいつも通りよ」
ふいに沸き上がってきたそんな気持ちに戸惑ってしまい、わざと不機嫌な口調を作る。
「そうか、君がそう言うんならいいんだけど。ただ、採取場の奥まで入ってから動けなく
なると困るからね」
ヴィトスは、ふう、と大きなため息を吐いた。
「僕は、座り込んで動けなくなった君を負ぶって帰るのは嫌だよ。まあ、背負った所で
持ち上がらないかもしれないけれどね」
体重の事を言われているのだと受け取ったユーディーは、カチンと来て言い返す。
「失礼ねっ、あたしはそんなに重くありませんー、だっ! あたし一人くらい負ぶえないで
どうするのよ、そんな軟弱でヒヨワな男なんかモテないんだからねーだっ」
ぷんぷんと怒り出すユーディーを見て、ヴィトスはぷっと吹き出した。
「良かった、それくらい元気があれば大丈夫。いつものユーディットだ」
ヴィトスは立ち上がると、軽くのびをした。それからまだ座ったままでいるユーディーを
少し見下したような目付きで眺める。
「ユーディット。いつまで僕のマントの上に座っているんだい?」
「へ? あ、あっ、ゴメンっ! ……って、ヴィトスが座れって言ったんじゃない!」
そう言いつつも慌てて立ち上がり、マントの端を持ってぱたぱたと草を払う。
「ほら、早く返してくれ」
「言われなくても返すわよっ」
投げ付けるように渡されたマントを受け取ると、少々シワになったそれを身に纏う。
「じゃあ、試してみようか」
「試すって、何を?」
「僕が君を負ぶえるかどうかさ」
「え。別にいいわよ」
手を振るユーディーに背を向け、ヴィトスは少しかがみ込んだ。
「いや、ヒヨワだのモテないだのとは思われたくないからね。ユーディットくらい軽く
持ち上げられる所を見せておかないと」
「何よそれ、何でそんなに大きな話しになってるのよ」
振り向いたヴィトスは、顎をしゃくってユーディーをうながす。
「ううう。分かったわよ」
照れくささをごまかしながら、ゆっくりとヴィトスの背中に近付いて彼の肩に腕を伸ばす。
ユーディーの指先がわずかに肩に触れた瞬間、さっと振り向いたヴィトスはユーディーの
身体を正面から抱きしめた。