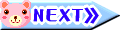● からかわれて、戸惑って (同人誌より再録)(1/3) ●
「ふうー、やっと取りあえず、大きい荷物だけは片づいたなあ。これでなんとか調合作業は
始められるかな?」
ヴェルンからメッテルブルグに引っ越して来たユーディーが、それでもまだ細かい道具や
材料を仕分けた入れ物などがごちゃごちゃしている部屋の中を見回して、ふう、と
ため息を付いた。
「えっと、中和剤をあまり持って来なかったから、まずそれから作らなくちゃいけないな。
後は調合に必要な材料を買い足して、っと。買い忘れをしたり、うっかり無駄な物
買ったりしないように、いる物をきちんとメモして行かなくちゃ」
カゴの中に無造作に突っ込んであるゼッテルをメモ用紙代わりに取り出す。そのゼッテルを
テーブルの上に広げ、椅子に座ってペンを走らせていると、コンコン、とドアを叩く音が響いた。
「はいーどなた?」
書きかけのゼッテルとペンを放り出し、立ち上がってドアに近づく。ドアを開けると、
「やあ、ユーディット!」
珍しく部屋に入る前にノックをしたヴィトスが、ユーディーの目の前で笑顔を作った。
「な、何よ。借金の取り立ての時期には、まだ早いと思うけど?」
この男がこんな風に笑うのは何か企みがあっての事だ、そう思ったユーディーが
今すぐにでもドアを閉めてしまいたい衝動を抑えつつも、あからさまに不信感を声に出す。
そんなユーディーの不機嫌そうな声にはかまわずに、
「いや、取り立てじゃないよ。今日は君の貴重な時間を僕の為に使ってはくれないかな、と
思ってね」
ヴィトスは眼鏡の奥で目を細め、優しい声を出した。
「えっ?」
それを聞いたユーディーの顔が思わず熱くなる。
(えええっ? それってもしかしてデートのお誘い? いや、でも、ヴィトスの言う事よ、
素直に受け取っちゃいけないわ。きっと何か裏があるはずよ。そもそもこの世界で
暮らしていく為のお金を簡単に立て替えてくれたのだって、後からたっぷりと利子を
取る為だったみたいだし)
なんとか冷静にヴィトスの本音を見抜こうと努力するユーディーに、
「ふふ。今日は僕が色々な所へ連れて行ってあげようと思うのだけれどねえ」
ヴィトスがまた魅力的な提案を口にする。
(色々な場所へ連れて行ってくれる? それじゃ、やっぱりデートに間違いないわよね。
ヴィトスってあたしの事、デートに連れてくような、そんな風に思ってくれてたのかな……)
ヴィトスが、デートに誘ってくれた。そう思うとユーディーの胸がドキドキと高鳴ってしまう。
「本当? うーん、どうしよっかなあ?」
両手を背中で組み、わざともったいぶって素っ気なさを装うが、
「都合が付かなかったら別にかまわないんだが」
「あ、行く! 行くわ」
ヴィトスが帰ってしまいそうな素振りを見せると、ユーディーは食いつくように返事をした。
「そうと決まれば早速行こう。お手をどうぞ、お姫様」
(お、お姫様、ですって?)
心の中できゃあきゃあと叫んでいるユーディーの手をヴィトスはそっと取った。
ヴィトスの方は手袋越しとは言え、もちろん男性と手をつなぐのは初めてのユーディーは
顔を赤らめてしまう。
「では、まずは街で一番の雑貨屋へ!」
元気のいいヴィトスの言葉に、
「えー、雑貨屋さんに行くのー?」
少しがっかりした声が出てしまう。
(デートって、もっと素敵な所にエスコートしてくれるんじゃないのかなあ)
「まあまあ。軽く買い物さ。買い物好きだろう?」
「うん、好きだけど」
(そっか、ウィンドウショッピングをして日が暮れてから流行りの店でお夕食を食べて、
ムードが出てきた所で石畳なんかを歩いちゃって、そ、それで愛の告白なんか
されちゃったりして……)
一人でどんどん勝手に空想がふくらんでしまい、ますます顔が赤くなるユーディーの
手を握ったまま、ヴィトスは部屋を出て黒猫亭に降りた。
(こんな所、クリスタやアデルベルトに見られちゃったら、どうしよう)
ヴィトスと手をつないでいる所を見られると恥ずかしくて困ってしまうような、でも
ちょっと見られたいような気もしたが、黒猫亭には見知った顔は一人もいなかった。
そのまま黒猫亭のドアを出て、中央広場に向かう。
(ラステルがいたらなんて言い訳しよう。別にヴィトスと付き合ってる訳じゃないけど、
あっ、これから付き合う事になるのかなあ。そうしたら、親友のラステルにはきちんと
話しておかなくちゃだめだよね)
人ごみをきょろきょろ、と見回すが、いつもなら自分の顔を見つけると嬉しそうに
駆け寄ってきて挨拶してくれるラステルの姿は見えない。ほっとしたような、少し残念な
ような気持ちでヴィトスの方に視線をやると、
「どうしたんだい? ユーディット」
ヴィトスがにっこりと笑う。
「や、なんでもないよ」
それに釣られてユーディーも微笑んでしまう。
中央広場から階段通りへ、石の階段を降りる。雑貨屋のドアを開けて中に入ると、
「ちょっと待っててくれ」
ヴィトスはそう言ってユーディーの手を離した。
(あれ? どうしたのかな)
自分の手からヴィトスの体温が失われ、手のひらにほんのわずかの寒さとさびしさを
感じる。だからと言って自分から手をつなぎたいとは言えずに黙っていると、ヴィトスは
ユーディーを入口に残して店の奥、雑貨屋の主人のいるカウンターまで歩いて行ってしまった。
一人で取り残されたユーディーは店の主人となにやら話しを始めてしまったヴィトスの
後ろ姿をぼんやり見ていたが、彼が戻って来ないので雑貨屋の商品棚に置いてある物を
眺める事にした。
しかし店の陳列棚に並んでいるのはいつもと同じ代わり映えのしない商品ばかりで、
とりたてて目を引く物がある訳でもなく、それにもすぐに飽きてしまう。
「ねえ、ヴィトス〜」
話しをしている邪魔をしてはいけない、と思いつつも、ヴィトスに近づいて彼のマントを
小さくつかみ、それをくいくい、と引っぱりながら甘えた声を出す。
「ああ、もう終わるよ、ユーディット。それでは……」
店の主人に挨拶をして、またヴィトスがユーディーの手を取る。
「えへへぇ」
くすぐったそうにヴィトスと手をつなぐ。
「それでは次は……武器屋。メッテルブルグの武器屋はフィンデン王国一の規模だからね」
「えっ、武器屋? なんでえ?」
「うん、何か掘り出し物があるかもしれないからね」
(デートで武器屋かあ。まぁ、別にいいけどねぇ)
変わったデートだなあ、と思いつつ、雑貨屋のすぐ斜め向かいにある武器屋に向かう。
店に入るとまたヴィトスはユーディーを置き去りにして、店の主人と話しを始める。
(なんなのかしら、もう)
武器や鎧、素晴らしく出来のいいフラムなどを見て時間つぶしをしていたが、だんだん
ふくれっ面になるユーディー。
「お待たせ、ユーディット」
それでも笑顔を見せるヴィトスの手が自分に向かって伸びると、
「うん」
素直に自分も手を差し出してしまう。
「それじゃ、行こうか」
(これからお食事に行くのかな?)
わくわくするユーディーの思いに反して、ヴィトスの足は黒猫亭に向かった。
(ワイングラスを傾けながらお食事? でも、黒猫亭じゃなあ)
せっかくだから普段自分一人では入れないようなお洒落なレストランとかに連れて行って
欲しいのになあ、とユーディーが少ししょんぼりしていると、ヴィトスはさっさと階段を
上がってしまう。
「えっ?」
驚くユーディーの目の前で勝手に部屋のドアを開け、
「それじゃ買い物はおしまい。今日は色々助かったよ」
ヴィトスが小さく頭を下げた。
「ええっ、買い物?」
「うん、買い物」
「そ、それってどういう事よ! あたし買い物に付き合わされただけって事?」
笑顔のヴィトスがこくん、と頷く。
「だ、だってそんな! デートじゃなかったの?」
「デート? とんでもない。今日は交渉ごとがあってね、一人だと警戒されるから女の子を
連れて行きたかったのさ。君のおかげで有利に交渉が運んだよ」
「とんでもないって……、あたしのおかげ、ってどういう意味よ!」
訳の分からない事を言われ、ユーディーの声は荒くなっていく。
「店主との話しの途中で、君が僕にちょこちょことちょっかいを出してくれただろう、
あれは良かったよ。向こうは僕の事を軟派な優男だと見くびったらしくてねえ、
普段なら外に漏らさないような美味しい話しを教えてくれたよ」
「何よそれ! あたし、てっきり……ひどーい!」
拳を握ってヴィトスを叩こうとするが、
「ああ、そうだ、これはお礼だよ。君のおかげで本当に助かった」
ヴィトスはユーディーが握っている手を簡単に押さえてしまう。手を広げさせ、その上に
コールを落とした。
「お礼、って」
「それじゃ!」
「ちょ、ちょっと待ってよ、ねえ!」
ユーディーの声を無視して、爽やかな挨拶を残してヴィトスは去ってしまった。
「……」
納得がいかないまま、ユーディーは部屋に入って帽子を脱ぎ、それをテーブルに置く。
「な、何よ、何なのよ、いったい! あたし、仕事のダシに使われただけって事?」
改めて釈然としない思いがこみ上げて来たユーディーは、拳をきつく握り直し、ついでに
だんだん、と床を踏みならした。
「それに、お礼って」
手を開けると、そこにはほんのちょっぴりの小銭が乗っているだけだった。
「何よこれ、子供のおこづかい? これっぽっちじゃレヘルンクリームだって買えない
じゃないのよ、もうっ、し、失礼しちゃうわ!」
この怒りをどこにぶつけたらいいのか分からず、取りあえずの腹立ち紛れに、うきーっ、と
うなりながらコールをテーブルに叩き付ける。
「ほんとに……、全く……」
ふと空になった手を見つめ、
「でも、ヴィトスに手をつながれちゃったなあ」
そう思うと、ぽっ、と頬が赤くなってしまう。
「でっ、でも、それはお仕事の作戦だったのね!」
仕事の為なら手段を選ばないヴィトスの根性の悪さに、改めてふつふつと怒りが沸き上がるが、
照れてしまった自分、てっきりデートに誘われたと思い込んで舞い上がっていた自分にも腹が立つ。
「もうっ、ムカつく! 寝る!」
上衣を脱いでベッドの隣りの背の低い木のチェストにぞんざいに放り投げる。
ユーディーは布団に潜り込んで背中を丸めてぎゅっ、と目をつぶった。無意識のうちに
ヴィトスに触れられていた手を胸に当て、反対側の手のひらでそれを覆う。
「なんなのよ、いったい……」
ヴィトスにつながれた手の指先がいつまでも熱く火照っているような気がして、
なかなか眠りに入ってはいけなかった。
◆◇◆◇◆