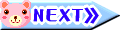● 思わせぶりなプレゼント(1/2) ●
事の始めは、三ヶ月前だった。
借金の利子代わりにひとくちだんごを取り立てられ、拗ねてそっぽを向くユーディー。
「ユーディット、そんなに怒らなくてもいいだろう?」
「うるさいなあ、別に怒ってないわよ」
そう言いながらも口調はとげとげしい。
「そうか。だったら別にいいんだ」
声に含まれた嫌みをわざと無視して、ヴィトスはうんうんと頷く。そんな不敵な態度に
余計に腹が立ち、もう一言二言言ってやろうかと口を開きかけた時。
ふいにヴィトスはユーディーの手を取り、それを自分の口元へと持って行く。何を
されているのかユーディーが認識する前に、ヴィトスはその小さな白い手の甲に
軽い口づけを落とした。
「……」
「用事は済んだし、僕は退散するよ。じゃあな」
そして、何事もなかったように短い挨拶をすると、呆然とするユーディーを残して
さっさと部屋を出て行ってしまったのだった。
「……えっ?」
部屋に一人になり、数分が経った頃。やっとユーディーは口を開く。
「今、ヴィトス何したの? あたしの、手」
ゆっくりと手を自分の目の高さにまで上げ、ヴィトスにくちびるを付けられた場所を
じっと見つめる。
「嘘」
彼のやわらかいくちびるを感じた部分、それと首の辺りからじわじわと熱がこみ上げ、
身体中に広がっていく。
「ヴィトス、あたしの手に、キス……したよね。それともあれってただの挨拶?」
挨拶の代わりに手の甲にキスをするという行為が存在するのは知っている。
「でも、そういう挨拶するのって、昔の人や貴族や上流階級よね、きっと。でも、
ヴィトスにはそんなの一度もされた事無いし」
もちろん、ヴィトスが他の人の手にキスをするのも見た覚えはない。
「どうしたのかしら、突然。それとも、あれはキスじゃなくて、ただ単にあたしの
勘違いなのかしら」
胸の鼓動が勝手に早くなり、頭がクラクラする。彼にされた行為の意味を考え、しかし
頭のどこかがそれを認めたがらずに理由を見出すのを拒否しようとしている。
「ヴィトスは何か違う事を……、そうだ、あたしの手の味を見たくて舐めてみた……、
って、なんでヴィトスがあたしの味見をするのよ」
一人でぼけて、一人で突っ込んでみる。
「まあ、きっとヴィトスの気まぐれね。そうでなければ、またあたしをいじめるネタを
思いついた……、あっ、それだ。きっとそれよ!」
ここで慌てたユーディーが口づけの意味を問いただしに行けば、いつもの人を馬鹿にした
ような態度で、ネチネチと意地の悪い嫌みを言われるのだろう。
「ふふん、その手には引っかからないもんね。ああ、ヴィトスの悪巧みに気付いて良かった。
ああいうのは相手にしないのが一番よ」
独り言をつぶやきながらも、いつまでも胸の熱っぽさは収まらなかった。
それから一ヶ月後。今から二ヶ月前の事。
またもや利子を取られ、頬をふくらませるユーディー。
しかし心の中は、取られたメテオールよりも前回の口づけの事でいっぱいだった。
(今日は隙を見せないようにしなくっちゃ)
ユーディーは両手を背中に回し、しっかりと組んだ。
(でも、何か言ってくるかなと思ったのに)
前回の取り立てから今日まで。酒場や道で顔を合わせても、つまらない話しはするものの
その件に関しては一言も触れられなかった。
(やっぱりヴィトス流の意地悪だったんだわ。無視して正解だったのね)
そう思いながらも、何かあるのではないか、意地悪ではなく、もしかしたらヴィトスは
自分に好意を寄せてくれているのではないか……、そんな風にも考えてしまった。
(でも、ヴィトスがあたしを好きだなんてある訳ないもの。いつもいつも、いーっつも
あたしの事いじめて喜んでるんだから)
今日だって利子を取られる前にたっぷりとお説教をされた。勝手にカゴを漁り、そこに
たまたま入っていた使いかけのメテオールを見つけて取り上げたのはヴィトスなのに、
品質が悪いだの、変な臭いがするだのと言いがかりを付けられたのだった。
「ユーディット」
「……何よ」
名前を呼ばれ、顔を上げる。
「いや、余りに間抜けな顔をしていたから、ちゃんと生きているのかと思ってね。
たまにぼんやりする位ならいいけれど、借金を返すまではきっちり働いてもらわないと」
「そんな言い方しなくてもいいでしょ、失礼ねっ。あたしだって頑張ってるわよ、
利子が暴利で悪徳で非道だから返せないだけで!」
ぴりぴりと緊張していた気持ちを刺激され、いつも以上に言い返してしまう。しかし、
ユーディーがむきになればなる程、ヴィトスは面白がるのだった。
「ふうん。君はそういう口の利き方をするんだ」
「別にあたしがどんなしゃべり方してもいいでしょっ」
「うん、まあ、確かに別にかまわないけれどね」
口の端で笑みをこらえ、ヴィトスが頷く。
「用事は済んだんでしょ、だったら帰りなさいよ」
「ああ、もう帰るよ」
今日は何となく無事に済みそうだと思い、ほっとする。同時に、心の隅で何かを期待して
いる自分に気付き、それを認めたくなくて変な方向に流れそうになる思考を押し殺す。
「今度はもっといいアイテムを用意しておいてくれよ。まあ、借金を返してくれるのが
僕にとっても、君にとっても最善だとは思うけれど」
ヴィトスは大股で数歩歩き、ユーディーの正面に立つ。先ほど一瞬気を抜いてしまった
ユーディーだったが、自分に近付いてくる彼を見て自分の後ろで組んでいる手に力を入れる。
ヴィトスはユーディーの細い肩に手を置くと、そのまま無防備なおでこに顔を寄せ、
そこに軽く口づけた。
「……」
「じゃあな」
それから、やはり以前と同じようにそっけない挨拶をして部屋を出て行く。ユーディーは
為す術もなく、振り返ったヴィトスの背中を目に映していた。
やがて、ぱたんとドアが閉まり、
「……う、あ」
その音でやっと我に返って短いうめき声を上げる。
「そ、そんな」
おでこに触れようとしたが、燃えるように熱くなった肌で火傷をしてしまいそうな気がして、
やり場のない手を落ち着きなく降ろしたり上げたりする。
手の次は、おでこ。
「何なの、何なのよ、いったい」
今にもくたくたとくずおれそうになる足にできる限り力を入れ、何とか持ちこたえる。
「何の冗談なの、何の嫌がらせなの、これ?」
胸の奥からこみ上げて来る熱い固まりが喉を塞ぐ。ヴィトスの訳の分からない行為に対する
怒り、疑問、戸惑い。そして、かすかな気恥ずかしさと、嬉しさ。
「嬉しい……? う、嬉しくなんかないっ」
ぶんぶん、と首を振ってみるが、一度気付いてしまった感情は簡単に消せない。それどころか
認識してしまった為に余計にその気持ちが際だってくる。
「訳分かんないわよ。……もう、あんなヤツの事なんか考えない! 考えないのが一番!」
そう口に出して自分に言い聞かせても、揺れる心は収まらなかった。
そして、つい一ヶ月前。
前に傾けぎみに深く被った帽子の縁で前髪を押さえ付け、できる限りのガードはした。
「でも、まさかほっぺにされるなんて」
利子の取り立て、突然のキス、そして何事もなかったように部屋を出ていくヴィトス。
「あたしをからかうって言っても限度があるわよ。こんな、こんなのって酷い」
一人になった部屋で、心を引っかき回すだけかき回され、荒れ狂う感情を持てあました
ユーディーの瞳にじわり、と涙がにじんでくる。
「あたしの事が、す、好きだったら好きって言えばいいじゃないの。なのに、何で
あんな思わせぶりな事をするのよ」
正直、手にキスをされる前からヴィトスの事は嫌いではなかったが、不可解な行為を
重ねられる度に、一日の中で彼を想う時間が増えていった。
外でヴィトスに会う度に、何か説明をしてくれるのではないか、何か然るべき言葉、
ユーディーが欲しいと思うようになってしまった言葉をくれるのではないかと淡い
期待を持ってしまう。しかしいつも期待は裏切られ、こっちの気持ちだけが空回りする。
「あたし、あたしだって、ヴィトスが」
ヴィトスが……好き?
「違う。違う……筈よ。でも、分からない」
ユーディーはのろのろとした足取りでベッドへ行くと、そこにどさりと座る。膝の上に
肘を乗せ、背を丸めて熱くなった頬を両手で包む。
「分からないけど、苦しいよ」
たった一言だけ。彼が自分の事を『好き』だと言ってさえくれれば。
ヴィトスの気持ちが分かった上でもらうキスならば、きっと幸せな気持ちになれるに違いない。
しかしこんな不確かな状況で、落ち着かない感情だけを与えられて放り出されるのは耐えられない。
「こんなの、もうやだ。嫌い、ヴィトスなんか嫌い」
どくどくと痛いくらいに高鳴っている心臓。
手の甲、おでこ、そして頬。彼のくちびるが触れた部分に、順番に意識を巡らせる。
「あっ」
そして、気が付く。
「も、もしかして」
徐々に移っていく場所。それは本当のキスをする場所、くちびるへと向かっているのでは
ないだろうか。
「そんな、このまま来月になったら、あたし」
彼の気持ちが分からないまま、自分の気持ちを告げないまま。初めてのキスをされて
しまうかもしれない。
「だめ、そんなのだめよ」
拳を握り、くちびるに押し当てる。
「どうしよう、こんなの誰にも相談できないし、そもそもヴィトスの意志が分からないし。
……そうだ! 今度ヴィトスが来る前までに借金を返しちゃえばいいんだ」
良い考えのように思えたが、現在の所持金と五万コールの間には遠い隔たりがある。
今までユーディーがお金を稼いでいたペースを考えると、とてもではないが間に合わない。
「困ったなあ、このままじゃ、きっと……キス、されちゃうよ」
ヴィトスに抱かれ、キスをされている自分を想像すると、かああっと頬が熱くなる。
「でも、されても、いいかな……、だめ、だめよ! あたしったら何考えてるの?」
いつまでもユーディーの不安は消えなかった。
◆◇◆◇◆