�@���@��ȉו�(1/2)�@��
�u���āA���ꂶ��o�����܂��傤���v
���F�����̎���ɂ������B�g�X�ɐ��������A���[�f�B�[�͂ɂ�����Ɣ��B
�u�o��������āA�ǂ��ցv
�u�ǂ��ւ��āA���b�e���u���O���ĊX�ւ�B��q�A��낵���ˁv
�u��낵���˂͂�������ǁc�c�v
�������[�f�B�[����Ɏ����Ă���̎�J�S�͂����B���B�g�X���ڂ𗯂߂��̂́A�ޏ���
�w�����Ă���A�R�̂悤�ɑ傫�ȃ����b�N�T�b�N�������B
�u�ׂ�̒��֍s�������Ȃ̂ɁA�����Ԃ�Ƒ�ו����ˁB�����z������ł������Ă���̂����H�v
�u����Ȃ̓����Ă��Ȃ�����Ȃ��́B����͍Œ�K���i��v
�u�ӂ���c�c�H�v
�Œ�ƌ�������ɂ͑傫������悤�Ɏv�������A�����K�v�Ȓ��ւ���ѕz�ł��l�ߍ����
����̂��낤���B
�u�l�������Ă��������H�@����ȑ�ו������ς��낤�v
�u������A�����Ŏ��Ă邩����v��v
������ɐU��B
�u�������B�r���Ŕ��ċC���ς���āA�w�����b�N�������ė~�����x�Ȃ�ĊÂ��Ă��A
�@���̎��͂����x�����B�����Ă��Ȃ�����ȁv
���炩���C���Ƀ��B�g�X�������b�N�Ɏ��L�����Ƃ��邪�A���[�f�B�[�͐g�̂�
�Ђ˂��Ă��̎������A
�u���C��B����ɁA����͑�ȉו��Ȃ���A���̐l�ɔC����C�͂Ȃ����́v
�����ς�ƌ��������B
�u�ѕz��������l�������Ă��邩��A�����]���ȉו�����������u���Ă��Ă��������v
����ł����B�g�X�͔ޏ����C�������A
�u�����A�ѕz�H�@�ѕz���āA�����ĂȂ���v
����Ƃ�A�Ƃ����ڂŌ��߂��Ă��܂��B
�u�ѕz���Ȃ����āA�N�͖�ɂȂ�����g�̂ɉ��������Ȃ��Ŗ���C�������̂����v
�u���[�A���[�ƁA�ł����B�g�X�������ĂĂ���Ă��ł���H�@�������炢������Ȃ��v
�u����ɁA�ѕz���Ȃ��ł��̉ו��́A��́v
�u�܂��܂��A��������Ȃ��B�o���A�o���`�v
�������ƃ��B�g�X�̘r��͂݁A���[�f�B�[�͂��������ƕ����n�߂��B
���[�f�B�[�ƈꏏ�Ƀ��F�����ɗאڂ��Ă���̎��ɓ���A���ɐ����Ԃ��߂��������Ȃ�
���x�����������A���������ė�������̂͏��߂Ă������B
�u�N�́A�{�i�I�ɊX�̊O�ɏo��̂͏��߂Ă�������ˁv
�ޏ��Ə��߂ĉ���āA���F�����ɘA��Ă��āB�h�̐��b�����Ă���Ă���A�ޏ���
�X�̊O�ɏo�����͖������������B
�u����A�������h�L�h�L����Ȃ��B�ł��A���B�g�X���ꏏ�����畽�C�ł���H�v
���ǂ��Ȃ���łɂ�����Ə��B
�u�����A�������ȁv
�܂������͔ޏ��Ɋ��S�ɐM������Ă��Ȃ��A����͊����Ă��邵�A�ޏ����o����ĊԂ��Ȃ�
�l�Ԃ��ȒP�ɐM�p����悤�Ȗ��ł͂Ȃ��͉̂��ƂȂ��������Ă���B
����ł����[�f�B�[�����܌�����P���悤�Ȕ��݁A������̐S�܂łƂ낯�Ă��܂�������
�Ί����������ƁA�����ޏ��̐M�������Ƃ����C�����ɂȂ��Ă��܂��B
��A�O�C�̂ՂɂՂɂ��������x�ŁA���ɏ�Q���Ȃ�����i��ł����B
�u�������y�����ˁB���̃y�[�X����A��ɂȂ�O�Ƀ��b�e���u���O�ɒ������Ⴄ�����ˁv
�u�������ɂ���͂Ȃ��Ǝv������ǂˁv
�ŏ��̂����͌��C�����Ɍy�����������Ă������[�f�B�[���������A�X���痣��čs���ɘA��
�ܑ�����Ă���ӏ��������Ȃ�A��v�ȓ��Ƃ͂����R���ɋ߂��悤�ȓy���ɂȂ��Ă���ƁA
�r�[�ɍ����グ��B
�u�����������A��ꂽ��`�v
�u�������̐����͂ǂ��������B�����A���b�e���u���O�ɒ����낤�H�v
�u�������A���B�g�X�������B�����A�����ɂ���v
�X�˂��悤�ȓ������B�g�X�����グ��B����Ȋ�����Ă���{�l�͋C�t���Ă���Ă���̂�
�ǂ��Ȃ̂��A���܂�ɉ��炵���\��ɁA�������B�g�X���D�����C�����ɂȂ��Ă��܂��B
�u�������A�������班����������ǁA�����͂����x�ނƂ��悤���v
�u������ˁI�@���B�g�X�b����I�v
�ς���Ǝ��@���A���������ɔ��ށB
�u�˂��A�L�����v�����ł���B�ǂ��ŐQ��́H�@���̖̉��͂ǂ����ȁH�v
�傫�Ȗ̍��{���w�����A�����Е��̎�Ń��B�g�X�̑������������ƒ͂B
�u���ꂾ���͂��Ⴎ���C������A�������������邩�ȁv
�u���߂��A���߂��߁A�����Ȃ��I�@�L�����v����́A�L�����v�B�˂��˂��A��������
�@���A���ۂ��̂����邯�ǁA���A�ŃL�����v�H�v
�ǂ����A���߂ẴL�����v�ɋ������Ă���炵���B
�u�ǂ���ł���������ǂˁB���ꂶ��A���̖̉��ł��т�H�ׂāA���A�̒��ŋx�ނƂ��邩�v
�u����A�������܂���B��[���A�L�����v���A�L�����v�v
�������q�O��ȕ@�̂��̂��Ȃ���A���[�f�B�[�͑����Ŗ̉��ւƌ������Ă����B
�u�˂����B�g�X�A�����������v
�u�͂��͂��v
�}������A���B�g�X�͂����Ɍ��ǂ��B
�u���[�ƁA�����̔ӂ��т́c�c�A�������Ԃ̓��B�g�X�ˁv
�u�����A�l�Ȃ̂����H�v
�����J�����ꏊ�ɂ�������ŏW�߂��ׂ��͖�g�݁A��t����B���̊ԁA���[�f�B�[��
�傫�ȃ����b�N�����낵�A�w�L�т������肵�Ă��낢�ł����B
�u�������ł���H�@�����ł��Ȃ������炠���������邯�ǁB�����A�ł������ɂ�
�@�B�������Ȃ���v
�u�B�������đ傰���ȁB�܂��A�l���݂ɐH�ׂ��镨�����Ȃ��͂Ȃ�����A
�@���Ƃ��撣���Ă݂�Ƃ��邩�v
�i�b�v�T�b�N�̒�����ȒP�Ȓ����p����o�����B�g�X�̎���A���[�f�B�[�͊��S�����悤�Ɍ��Ă���B
�u�����ޗ��͂��邩���H�v
�u���A�L�m�R�Ȃ玝���Ă�B�d���̓��P�v
�u�l�̓x�[�R���������Ă��邩��A�L�m�R�u�߂ł�����Ă݂悤���v
�K���ȑ傫���ɐ����x�[�R����M�����t���C�p������̓�ɗ��Ƃ��B�x�[�R���̖���
�o�����ō��x�̓L�m�R�����A��������Ƃ����B
�u�ȂA�����������ɂ����c�c�A�����v
���イ���イ�ƏĂ��鉹�A�������x�[�R���̖��̍���ɗU���A���������A��
���[�f�B�[�̂��Ȃ������Ă��܂����B
�u�R���v
�Q�ĂĂ��Ȃ����������A�����ƃ��B�g�X�̊���f���B
�u�ǂ������H�v
�u������A���ł��Ȃ���v
�C�t����Ȃ��������A�Ƃق��ƋC���ɂ߂郆�[�f�B�[���������A
�u����Ȃɑ傫�����̒�����قǂ��Ȃ����Ă���Ƃ͂ˁB�Ȃ�ׂ��葁����邩��
�@�������������҂��Ă��炦�邩�ȁH�v
��������ꂽ��ɂɂ�ɂ���Ă��܂��B
�u�ȁA����I�@�����Ȃ�����Ȃ��́A�����v
�p���������̂��܂�j���M���Ȃ�A�Ƃ�B���Ō��t�������Ȃ�B
�u���ĂȂ���B����͖l�̗����Ɋ��҂��邠�܂�̎^���Ǝ���Ă������v
�^�ʖڂȌ���������Ă݂͂����̂́A��͂肱�炦���ꂸ�ɏ��o���Ă��܂��B
�u�������c�c�A���͂́A�������N�͖{���ɑf�����˂��v
�u���Ă�A���Ă邶��Ȃ��A���[���I�v
����������Ƀ��B�g�X�̘r��͂݁A����������������E�BK,�
�E�E�ҁE�������E�E�E���A�E
�E
A�E���E���E
��E�E�E�E�E�E�E
����E
��K
ƁE����
-
C,
�E���E��
,�E�E�E�E���E�E
���E��
R�
�<�R,�
@�E�E�E�ÖH�E
��E
��E�E
����E��E�E,�,�E��
��E�E
��� �8�<�K����E
�A�@���
�-�$����� ���)��� �"�R� �b�
����Ex��E���E
����E�E
�B�<
�B�<
�d��EB���Z������EH�J����EA�
��������E���
@��E%���(�I�A������E����<
�b����E!���+��Ek���`�<�I����E�E���EM��E
���%���+���B�H�I��E[����E�E�E��
�J�A�J��
�V�H�J�E
���������J������� ���J���<
��a����� ���> ���� �E��!���8������E���E����J����� ���I��E"��EB������E�E���E��K�B ��V��EJ��
���X��� ���(�����B ��< �%� �I���A���K�$� � �!�A��E�E���E��@�(�(����E) O����E�����������E����p
B�> ����E�E(� ���# B�� ���$����� ���C C��E �K���A��E����%��E��$����E��-�/�
���!��E����J����� �C��� � �J���� �- �d�����R������E�E�E� M ��E ��E����L�4����
�� �H�(�����.�a�J ��� B�� ��5� �#���� ����)���I��� ��������E�E���Ex�z�����
�I����E����.���v B�> ��q�m�K��� ����E�E�E\�[��Ev B�> �h����Ei���I�?�����?��E��h�����J
B�> �e�M���I�@���A�����������v B�> ���������>���������A��E���E�E����L�-�Z��E8�[�Z��Eh������E�EB
B�> �5�������������������� a���$��E�EJ�N� �*��E�E�����E����@�����!�T B��
� ���A�E���C� � ������E�� �����B�g�X������Ȃɗ�������肾�����Ȃ�āA�ӊO���Ȃ��v
�u�������A����͗ǂ������v
���B�g�X�͎����̎M�̗����Ɍ���t����B
�u�����̂��т����B�g�X�ɍ���Ă��炨�����Ȃ��B����Ȏ��Ȃ�A�����Ƃ����ȍޗ�
�@�����Ă���Ηǂ������ȁ[�v
�˂���悤�Ɏ��������߂Ă��郆�[�f�B�[�B���̕\����܂舤�炵���A���B�g�X��
�j���ɂ݂����ɂȂ��Ă��܂��B
�u����A�����͏��Ԃ��낤�B�����̂��т̎x�x�͌N�ɂ���Ă��炤�Ƃ����v
����ł����[�f�B�[�̍�����蒲����H�ׂĂ݂������B�g�X�́A�����ƌ����Ă̂����B
�u���[�A�����炱���ɂ͘B��������������c�c�v
�u�B�����������Ă��������炢���邾�낤�H�@����݂͑��Ă����Ă��������B����Ƃ��A
�@�N�̑傫�ȃ����b�N�̒��ɓ����Ă��邩�ȁH�v
�u���B�����ĂȂ��v
���̂������̃����b�N�������悤�ɘr��L���A�Ԃ�Ԃ�Ǝ�����ɐU��B
�u�����āA����Ȃɑ傫�ȃ����b�N������ˁB�l�̉ו���������ۂǒ��g���l�܂���
�@�����Ȃ����H�@�������g�������Ă���Ȃ����ȁv
�u���߁A���߁B����͌����Ⴞ�߁[���v
�Ў�ŎM���������܂܁A�����Е��̎�Ń����b�N��������߂�B�����܂ł����炳�܂�
��������ƁA��������Ӓn�������Ăł����g���������Ȃ��Ă��܂��B
�u�ӂ���A�������ȁB���������āA�l�Ɍ���ꂽ���Ȃ�����ł������Ă���̂��ȁv
�u�ʂɂǂ��ł���������Ȃ��A���B�g�X�ɂ͊W�̂Ȃ�����B���[�A�������������A
�@���������������������A�����������܁I�@���M�͐����́H�v
�ǂ��ɂ����Ęb���������b�N�����炻���Ƃ���B
�u�����A�����̐��Ő���āA�@���Ă����Ă���������B����A���͌N��
�@���ނƂ��āA�l�͂��̃����b�N���c�c�v
�u�����炾�߂����ĂI�@���ɂ������ĂȂ����A���Ă��ʔ����Ȃ����Ăv
�u�������Ȃ��v
�u�������Ȃ����v
���[�f�B�[�����炩���A���点��͔̂��ɖʔ��������B
���ǃ����b�N�̒��g�͌����Ă��炦�Ȃ��܂܁A�H���̌ォ���Â����I����B���ꂩ��
�A�Q�Ƃ����b���ɂȂ�A���B�g�X�ƃ��[�f�B�[�͓��A�̓����ɓ������B
�u�˂��˂��A���A�ŐQ��̂��Ăǂ�����́H�@���z�c������H�v
���Â����̒��������ƌ��āA���[�f�B�[���q�˂�B
�u�z�c�͂Ȃ���B�ѕz��g�̂Ɋ����t���āA���̂܂ܒn�ʂɐQ���v
�u���[���A����ȕ��ɂ�����A�g�̂��ɂ��Ȃ������Ȃ��H�v
���[�f�B�[�͎����̐g�̂�������߂�B
�u���ꂪ����������O�̂��炩�����̏�ŐQ�Ă����܂�Ȃ�����ǂˁB�܂��A�钆��
�@���肱���Ă���ԂɁA�N���ՂɂՂɂ₭�܂ɐH�ׂ��Ă��l�͊֒m���Ȃ�����ǁv
�u�������A�H�ׂ���̂͌��`�v
���Ȃ��Ă��郆�[�f�B�[�̓����A�ۂ�ƌy���@���Ă��B
�u���̓_���A�̒��Ȃ���S���낤�B�����ɖ�������̉�u���Ă����A���܂�
�@�����Ă��Ȃ����낤���v
���B�g�X�͈�x���A�̊O�ɏo��ƁA�����̒�����K���Ȏ}���݂�����Ď����Ă���B
�������A�̒��ɗ���Ȃ��悤�ȏꏊ��I�сA�����ɏ����ȕ�����������B
�u�܂��A���̉������Ă��܂����A���A�̉��ɋ��\�ȃ����X�^�[�����邩����A������Ԃ�
�@�Ȃ��ς�����H�ׂ��Ă��܂����낤����ǂˁv
���̕ӂ�ɂ͂���Ȃɋ��\�ȓG�͂��Ȃ��̂ŁA�Q�Ă���Ԃɕ����������Ă��܂��Ă�
���܂���͂Ȃ��B�����m���Ă��ă��[�f�B�[��|���点��悤�Șb���𑱂���B
 �@�@�@
�@�@�@  �@�@�@
�@�@�@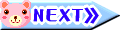 �@
�@