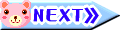● 腕の中の小さなキス(同人誌より再録)(1/2) ●
ユーディーの部屋に向かっていたヴィトスは、狭い廊下で錬金術士の女性とすれ違った。
冷たい青い色のドレス、何より左右色の違う瞳は印象深く、他の誰かと見間違う事はない。
ユーディーの元で何度かパーティーを組んだ事もある錬金術士のヘルミーナだった。
軽く会釈をすると、
「とりあえずの所は成功と言っても良さそうね。後は、時間の退行における試薬AとBの
バランスと持続性の確立……、あれではせいぜい二、三時間で効果が消えてしまう筈だわ」
ぶつぶつとつぶやきながら、ヴィトスの存在に気づかずにそのまま素通りして行った。
気を取り直して部屋のドアをノックする。
「ユーディット、いるかい?」
いつものように返事も待たずに勝手にドアを開けたが、そこにユーディーの姿は無かった。
その代わりにベッドの上に七、八歳くらいだろうか、幼いと言ってもいいような見かけをした
女の子がちんまりと座っている。
「おや?」
ヴィトスはふと自分の心の中に、その女の子に駆け寄り抱きしめたいという強い衝動が
沸き上がって来たのに驚いた。
(僕は小さい女の子をどうこうという趣味は無い筈なんだけれどな)
「えーっと」
その感情を払うように首を振るついでに、きょろきょろと部屋の中を見回す。
「何の用よ!」
ベッドの上の女の子が威嚇的ではあるが十分可愛い声で叫んだ。
「あ、これは失礼。お嬢ちゃん、この部屋に住んでる女の子がどこへ行ったか
知らないか? 名前はユーディットと言うんだが」
「……あたしよ」
「そうだな、髪は君と同じくらいの長さの銀色で、君がまとってるのと同じような
赤い色の服を着て、君のと同じような紫の丸いイヤリングをしていて」
「だからあたしだってば」
「ぼーっとした顔をしてて……、え?」
失礼な程にまじまじと少女を見つめる。
「あたしがユーディットよ、どうせぼーっとしてるわよ、悪かったわね! ヘルミーナさんに
薬を飲まされて背が縮んじゃったの! こんなにちっちゃくなっちゃったのよ!」
半分泣きそうな怒り顔でヴィトスを睨み付ける。
「いや、僕を睨まれても困るんだが」
(なるほど、この女の子はユーディットだったのか)
自分が密かに想いを寄せている少女の小さい時の姿を見て、あまりの愛しさに抱きしめたく
なったのも無理はないかもしれないな、そう考えたヴィトスはふいにおかしくなって、
ぷっと吹き出してしまった。
「な、何よっ。何がおかしいの?」
「いや、気にしないでくれ。思い出し笑いをしただけさ」
「人が困っているのに思い出し笑いなんて、ずいぶん余裕があるのね。あ、あたし、
ずっとこのままだったらどうしよう……、そんなのイヤよ!」
だぶだぶになってしまった服が肩からずり落ちないように両手でしっかりと押さえ、
首をぶんぶんと振る。
(薬の効果は二、三時間……)
なるほど、さっきのヘルミーナのつぶやきはユーディーが飲まされたという薬の内容に
関してだったのだろう。
「解毒剤とかもらってないのかい?」
「あの人が誰かに薬を盛る時に解毒剤なんて用意しておくと思う?」
「いや、思わないが……」
「でしょ?」
どうせ数時間で効果が切れるらしいから、と言いかけて言葉を飲み込む。
(まあ、こんなチャンスはめったに無いだろうからな。少しからかってやるとするか)
「そう言えば、さっき彼女とすれ違った時につぶやいていたのを聞いていたんだが」
「何?」
食いつくように身を乗り出す。
「……キスをすると、元に戻るらしいね」
「えっ、キスぅっ!?」
大声を上げてしまう。
「そ、そんなのある訳ないじゃない! ヴィトスったら適当ばかり言って」
真っ赤になってばたばたと手を振るユーディーに、真面目な顔で話しを続ける。
「だいたい昔から、悪い魔女の魔法はキスで解けるって相場が決まっているだろう」
「悪い魔女の魔法……、悪い魔女。うん、確かにそうかもしれないわね」
そこの所だけ妙に納得したユーディーが、うんうんと頷く。
「でもだからって、キスで治るなんてそんな訳ないわよ。嘘でしょ?」
「嘘だと思うんなら別にいいよ。君がずっとそのままの姿で暮らす羽目になるだけだから」
「うっ」
仕事柄、はったりをかますのには慣れているヴィトスは自信たっぷりな所を見せる。
その態度に押されたユーディーは言葉を詰まらせてしまった。
「どうする? 君はとっても困っているようだし、僕だったら協力してあげてもいいよ」
「きょっ、協力、って? まさか」
かああっとユーディーの頬が赤く染まる。
「ヴィトスが……、えっと、あたしとヴィトスがキスをするって事?」
ヴィトスがにっこりと微笑み、首を縦に振る。
「だ、だって、キスってそんな……、まだあたし誰ともした事ないのに」
小さな声でつぶやき、おろおろしているユーディー。
「どうするんだい? 永遠にそのまま、小さくなった格好でいたいのかい?」
「このままなのはいやだけど、でも」
「それとも他に誰か、キスしたい人がいるのかな」
他に好きな人がいるからヴィトスとキスをするのはいやだ、なんて言われたらどうしようと
内心でヒヤヒヤしつつ優しい声で尋ねると、
「他に誰かって、別にそんな人はいないけどでも、だからって」
照れた顔をしながらそう返事をしたので、ほっと胸をなで下ろした。
「それでどうするんだい? ユーディット」
「ううぅ……、分かったわ、しょうがないもんね。ヴィトスにお願いする」
「よし。じゃあ早速抱っこしてあげるからお兄さんの所へおいで、ユーディットちゃん。
ほらほら、いい子だねえ」
ユーディーが座っているベッドの縁に腰かけたヴィトスが身体をひねり、楽しそうな顔で
彼女に向かって両手を広げる。
「なっ、何よその言い方! 分かってるわよ、言われなくても行くわよっ」
言葉の調子は荒いが、ベッドに立て膝になったユーディーの足は躊躇している。
「でも、ねえ、キスをするって言っても、どこにすればいいのかしら」
ふと、困ったようにヴィトスの顔を見上げた。
「うーん、どうなんだろうねえ」
ヴィトスは涼しい顔をしている。
「手とか? それともおでことか、ほっぺとにしなくちゃいけないのかしら」
「とりあえず試してみよう。おいで」
手招きをすると、ユーディーはおずおずと膝でヴィトスの前へと進んで来る。
「きゃっ!」
ヴィトスはユーディーの身体に手を伸ばした。細く小さい身体を優しく抱き寄せるてから、
ひねっていた自分の身体を戻しつつ、ひょいと膝の上に乗せてしまう。
「えっ?」
ヴィトスの突然の動きにびっくりしているユーディーを横抱きにして膝の上に落ち着かせ、
左手での背中を抱いて支える。
「では、まず手の甲に。ユーディットお嬢様、お手を失礼いたします」
「な、なによそれ」
照れるユーディーの手を取り、くちづける。
「治らない、わね」
「そうだねえ」
右手で彼女の額にかかった前髪をそっとかき上げる。
「次はおでこに」
「あ、えーっと……、うん。お願いします」
頬を染めて目を閉じるユーディーの額に、そっとくちびるを当てる。
「……治った?」
目をつぶったままのユーディーがヴィトスに尋ねる。
「うーん、治らないみたいだねえ」
治る訳がない。
「そっ、そんなあ」
泣きそうな顔になっているユーディーの頭をゆっくりとなでる。
「じゃあ、ほっぺにしてみよう」
「うん」
熱くなっているほっぺたにキスをしても、当然ユーディーの身体は元に戻らない。
「治らないねえ」
「えっ」
「やっぱり、ちゃんとくちびるにしなければいけないのかもしれないねえ」
その言葉を聞いたユーディーの目に、じわっと涙が浮かんだ。
「……いや」
「ユーディット?」
「だめ。だってそんなの、きちんと好きな人同士でするんじゃなくちゃダメだよ」
ずるずるとした袖で顔を覆って泣き出してしまう。自分の腕の中で小さな女の子が
哀しそうに背中を丸め、涙を流しながら震えている。
(しかもこの子は僕の大好きなユーディットなんだから)
好きな女の子が妙な薬を飲まされて不安になっているのに、からかった上に余計な
心配までさせて。
(いったい何やってるんだろう、僕は)
そう思った急にヴィトスは罪悪感に苛まれた。
「……ごめん、ユーディット。泣かないでくれ」
ユーディーはヴィトスの声も耳に入らないかのように、しくしくと泣いている。
「ごめんね、嘘なんだ。本当は時間が経てば元に戻るって言ってた」
正直にそう告げ謝ると、泣きはらした顔をがばっと上げた。
「な、なんですって?」
「二、三時間で効果が消えるって。キス云々と言うのは、僕の嘘だ」
と、次の瞬間、ぺちっと軽い音を立ててヴィトスの左頬にユーディーの右の拳が当てられた。
「僕が悪かった。いいよ、好きなだけ殴ってくれ」
今のユーディーが非力な子供の姿で良かったなあとぼんやり思いながら目をつぶると、
言葉通り遠慮せずに顔と言わず胸元と言わず、両手でぽかぽかと殴りかかってくる。
「……嫌い」
とりあえず気の済むまで殴ると、はあはあと肩で息をしながら、やっと涙の乾きかけた
目元に新しい涙を滲ませてヴィトスを睨む。
「ああ、すまない。ちょっと君をからかってみたかっただけなんだ」
「からかうって言っても、いくらなんでもやっていい時と悪い時があるわよっ」
「うん、そうだよね。でもあんなに泣いていやがるほど嫌われているとは思わなかった」
肩を落としてしまうヴィトスを見て、
「ヴィトス?」
首をかしげたユーディーが心配そうな声を出す。
「調子に乗りすぎたよ、本当にすまなかった。僕はそろそろ帰るよ」
膝の上のユーディーの頭を名残惜しそうに一回だけなでると、彼女の軽い身体をベッドに
降ろす。立ち上がりかけたヴィトスのマントのすそを、ユーディーの小さな手がつかんだ。
「なんだい? まだ殴り足りないのかい」
「べ、別に、ヴィトスの事、嫌いな訳じゃないわよ」
ちらっと振り返るヴィトスに、口ごもりながら話しかける。
「いや、いいよ。気を遣ってくれなくても」
「嫌いじゃないっていうか、むしろどっちかって言うと……って、なに落ち込んでるのよ」
「落ち込んでないよ、別に」
肩を落としてがっくりしている様子はどう見ても気を落としているようにしか見えない。
「嘘、落ち込んでるじゃない。なんであたしがあんたを嫌いだと、あんたが落ち込むのよ」
「別に落ち込んでないよ」
沈んだ声でヴィトスが答える。
「どう聞いても落ち込んでいる声だわ。そ、そんなにあたしとキスできなかったのが
残念だったのかしら?」
しょんぼりしているヴィトスを元気づけようと、努めて明るい声を出すが、
「ああ」
小さく、そう返事が返ってきてユーディーは驚いてしまった。