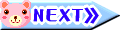● 深く結びつく想い(1/3) ●
!百合注意! 女の子同士のキスシーンがあります。苦手、嫌いな人は読まないで下さい。
「できた! ようやくできたんだわ、『竜の砂時計』が」
確実に作れる自信はあった。それでも、今あたしの手の中に存在している砂時計を
見ると不思議な感じがする。
「これで、過去に……、あたしの世界に戻れるのね」
あたしのいた世界。ラステルのいない世界。
あたしはゆっくりと砂時計を掲げ、自分のいた時代の事を強く念じた。
「……」
それから、だいぶ時間が経った。
「あれ?」
砂時計には何の変化もない。もちろんあたしにも、あたしの周り、工房の中にも。
「失敗、したのかな」
作っている途中の手応えから、そうは思えない。
「それとも、まだ何か足りない物が……、仕方ない、ポストさんに聞いてみるか」
このまま辛い気持ちとこの世界から逃げ出せるかもしれないって、一瞬でも思ってしまった
ずるいあたしに砂時計を使う資格なんてないのだろうか。そんな事まで考えてしまう。
その時、コンコンと軽いノックの音が聞こえた。
「はいー、どなた?」
「ユーディー! 遊びに来たよっ!」
ドアを開けたのは、眩しいくらいの笑顔のラステル。彼女の笑顔を見た途端、ぎゅっと
締め付けられる程に胸の奥が痛くなる。
「ユーディー?」
一瞬言葉を無くしたあたしを不審に思ったのか、ラステルは心配したような声を出す。
その時、あたしは思ったの。これはラステルの気持ちを知るチャンスかもしれないって。
「あっ、あはは、ラステルいいところに! あのね、これ見て。過去に戻る為のアイテム。
竜の砂時計、できたんだ」
乾いた笑いを浮かべながら、あたしはラステルによく見えるように竜の砂時計を持っている
手を上げた。
「まだ上手く働かないけどね。ちょっと工夫すれば使えるようになる筈なんだ」
あたしの言葉を聞いて、ラステルはどんな反応をするんだろう。おめでとうって言って
くれるかな? それとも……?
「アイテム……、できたんだ」
「うん、いろいろあったけどねえ。ラステルも本当にありがとう」
「そう、良かった」
それきり、ラステルは黙ってしまう。……それだけなの? 砂時計ができて、あたしが
過去に帰ってしまうかもしれないのにラステルは何とも思わないの?
「あ、あのさ」
「良かった。だってユーディー、夢だった……、もの、ね」
ラステルの瞳から、大粒の涙がこぼれた。
「ラ、ラステル?」
「ごめんね……、ごめんねユーディー。ユーディーがおうちに帰れるなら、喜ばなきゃ
いけない事だよね、それなのに私」
ひっく、ひっくとしゃくり上げながら、ラステルは続ける。
「私、本当は元の世界に戻るアイテムが見つからなければ……、ユーディーが過去に
帰れないままならって、酷い事思ってた、だって」
涙をこぼしながら、ラステルはあたしの目を見つめた。
「だって、ユーディーは私の一番大切な人だから! 私、私、ユーディーが」
もしかして、あたしがラステルを想うように、ラステルもあたしの事を想っていたの
かもしれないって、この時、そんな風に考えてしまった。
「ラステル、ごめんね、でも」
ラステルの事を、好きになってごめんね。でも、ラステルはあたしを受け入れてくれるの?
「いや……、いやよ! ユーディー、行っちゃいやあーっ!」
泣きながら、ラステルはあたしの胸に飛び込んできた。そのままあたしの身体をきつく
きつく抱きしめる。
「ラステ、ル」
ああ、ラステルもあたしの事が好きだったんだ。女の子を好きになるなんておかしいって、
ラステルはあたしを友達として見てるだけだからそんな変な感情を持っちゃいけないって、
ずっと一人で悩んでた時間がばかみたい。
「お願い、過去へなんて帰らないで。どこへも行かないで! ワガママも言わない、
ユーディーの言う事何でも聞く! 何でもするから、だから……」
あたしの胸に、ラステルの熱い涙と吐息が染み込んでくる。
「……ラステル、ごめんね。あたしはどうしても帰らなきゃいけないの」
口ではそう言ったけれど、それはもう一度、ラステルに引き留めて欲しかったから。
「……」
でも、ラステルは黙り込んでしまった。
「そう、そうよね」
……えっ?
「ダメだよね、ユーディーの幸せを考えるなら、本当にユーディーの事を、考えるなら」
新しい涙があふれている。ラステルのくちびるが震えてる。
「止めちゃ、ダメだよね。笑って、ユーディーにおめでとうって言わなくちゃ」
泣きながら、こっちの方が辛くなるような痛々しい笑い顔を作る。違うよラステル、
そうじゃなくて、あたしを止めてよ。あたしを好きだって、もっと言ってよ!
「私、人と別れる事ってあまりなくて。だからどうしていいか分からなくて、
取り乱してしまってごめんなさい」
ごしごしと涙をこすって、ラステルはまた笑顔を浮かべた。
「何だかユーディーが友達じゃなくなっちゃうような気がして」
友達、なの? やっぱりラステルにとっては、あたしはただの友達でしかないの?
「ラステル。これからも、あたしたち、ずっと友達……だよね?」
あたしの声だけが妙に明るく響く。ラステルに言いたいのはそんな事じゃないのに。
「二百年の時を越えた友達。これって、すごいよね……?」
ただの友達なんて嫌だよ。そうじゃないって言ってよ。友達なんかじゃないって。
「うふふっ」
まだ泣きながら、可愛らしく微笑むラステル。
「そうよね、すごいよね。きっと私達以外、そんな素敵な友達っていないわ」
……やっぱり、友達なんだ。ラステルはあたしの事、友達としか思ってないんだ。
あたしの想いは、彼女に届かなかったんだ。
「……」
「ユーディー?」
あたしは、ラステルを抱きしめた。
「そう、友達だよね。あたしとラステルはずっと友達だよ」
今のあたしにとっては一番自虐的な言葉。『友達』って口に出すだけで、心が張り裂け
そうになる。それでも、自分をあざ笑うようにその言葉を繰り返してしまう。
「ええ、ユーディー」
ラステルもあたしを抱きしめ返す。友達同士の抱擁。あたしが欲しかったのはこんなのじゃない。
「ねえ、ラステル。さっきラステル、何でもするって言ったよね?」
恋が破れて自暴自棄になったあたしは、ラステルの言葉尻をとらえる。
「え、ええ。私ができる事なら」
少し困ったようにラステルは頷いた。
「できる事ならいいのね。だったら」
あたしは、ラステルが驚く暇も与えずに、ずっと触れたかった彼女のくちびるに口づけた。
「……」
しばらく、時が止まる感じがした。
「……!!」
それから、身体をよじってあたしのキスと腕から逃れた彼女に、どん、と突き飛ばされる。
「う……、あ」
口元を押さえ、ラステルはさっきよりもたくさん涙を流してる。
「な、なん……、どうし、て」
真っ赤になっているラステル。愕然と目を見開いて。
「だって……、だって、あたしが帰らない為なら何でもするって言ったじゃない。
あたしの言う事聞くんでしょ、だったらあたしを好きになってよ!」
叫んでいるあたしの頭の隅では、この時点でもう何もかも終わったって、分かってた。
「す、好きよ。ユーディーの事は好き。だって、私達、友達じゃ……」
もう『友達』なんて言葉は聞きたくない!
「友達じゃないの! あたしはラステルが好きなの。ラステルを、ええと……、その、
恋人とか、そういう風に好きなの、女同士でこういうのおかしいよね、でもあたし、
ずっとずっと好きだったの、ラステルが!」
抱えてきた一気にぶちまけるあたしの心臓はばくばくと高鳴ってる。
「だから、ラステルもあたしを好きになってよ、あたしにキスをしてよ……」
声が震えて、かすれてしまう。
「私……、私」
ラステルの声も震えている。
「……そんなユーディーは、嫌いよ」
それは多分、ラステルが初めて口に出した、あたしを拒絶する言葉だった。
「うっ……、ひっく、ぐすっ……」
そのまま、ラステルは泣き続ける。
「ラ……」
名前を呼ぼうと思ったけれど、熱くて苦い固まりがこみ上げてきて、それがあたしの
喉を詰まらせる。
「う、ううっ……」
目元を手で覆って声を押し殺し、小さく肩を震わせているラステル。ぬぐってもぬぐっても
あふれる涙が頬にこぼれ落ちていく。
「ラステ、ル」
あたしはかすれた声で、ようやくその名前を口に出す。ラステルをこんな風に泣かせて
しまったのはあたしだから、あたしがなぐさめてあげなくちゃいけないって思って。
あたしの目の前で泣きじゃくるラステルは何も答えない。彼女の小さな手からこぼれた
涙は目元から頬、そしてあごへと流れ落ちていく。あたしはせめて頭を撫でてあげようと
して、鉛のように重くなった手をゆっくりとあげる。
「ひっ、く」
でも、少しだけ顔を上げたラステルの涙に濡れた瞳、驚いて、傷付いて、そして
怯えている瞳を見て、あたしの手が止まった。
「や……、いや」
あたしの手を見て、いやいやをする。
「触らないで」
その一言が、あたしの胸に先の鈍い槍のように突き刺さった。
「ごめ……」
ごめんなさい、と言おうとしたのにまた喉が詰まる。涙がこみ上げ、耐えられなくなる。
「……」
そんな事をしてはいけなかったのかもしれないけれど、あたしはラステルに背を向けた。
途端に涙があふれて止まらなくなる。どうしていいか分からなくて。
やがてラステルは、足音を立てないようにあたしから遠ざかったようだった。
かちゃり、とノブの回る音。ゆっくりドアが開く音。
「……あ」
そして、ぱたん、とドアの閉まる音。ラステルは部屋を出て行ってしまった。
「……」
ラステルの名前を呼びたかったけれど、口からは声にならない息だけが漏れる。
「あたし」
あたしは、ラステルが好きだったのに。彼女の心を傷付けるつもりなんかなかったのに、
……ラステルに嫌われるような事をするつもりはなかったのに。
それでもあの時、ラステルをあたしだけの物にしたいと思ったのも事実だ。
頭の中で、まとまらない考えがぐるぐると回っている。
「ラステル」
一つだけ分かっているのは、ラステルはもう二度と、あたしに笑顔を見せてはくれない
だろうと言う事。
「ごめん……、ごめんなさい、ラステル」
今更、しかも彼女がいない所で謝っても仕方がないけれど、あたしは彼女の名前を
繰り返さずにはいられなかった。
◆◇◆◇◆